┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/5/10 Vol.271 ━
┃☆ OPTRONICSメールマガジン ☆
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オプトロニクス社 ━
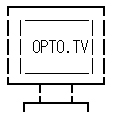
|
※ 科学の伝道者
※ 光の求人サイト「オプトキャリア」今週の募集案件
※ OPTRONICS ONLINE「オススメ記事/動画」
※ OPTRONICS Twitter/facebookのつぶやき
※ 今週のコラム「スワイヤーアイ」
※【6月8日】JOEM技術講座
「図解・光散乱入門 -自然現象から学ぶ-」
|
【facebook】 https://www.facebook.com/optronics.co.jp
がんばれ光技術 https://www.facebook.com/groups/1485309221797424/
【Twitter 】 https://twitter.com/optronics
|
セミナー「性能限界を突破へ!注目の非従来型バイオイメージング」
【5月29日】蛍光イメージングの性能限界を克服!【東京 四ツ谷】
http://www.optronics.co.jp/seminar/bi_01.php
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
科学の伝道者
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
5月2日,絵本作家の加古里子(かこさとし)氏が92歳でお亡くなりになりま
した。加古氏は東京大学を卒業後,研究者として昭和電工に勤めた後に作家
へと転身しています。天狗やダルマ,カラスを主人公にした絵本は世代を超
えるロングセラーとなったので,幼少のころ読んだ人はもちろん,子供に買
い与えたという方も多いでしょう。
私も両親から加古氏の本を贈られた一人です。ただ,記憶にあるのは童話で
はなく科学絵本です。中でも「海」「宇宙」「地球」の3部作は,幼ない私にと
って衝撃でした。「宇宙」は想像すら及ばない空間の広がりを,「海」は光さ
え届かぬ漆黒の深海を,「地球」は地下に渦巻く灼熱のマントルを,新たな世
界として畏怖と共に私の心に届け,刻みつけてくれたのです。
多作で晩年も創作意欲が衰えることのなかった加古氏ですが,「海」の執筆
を開始するにあったっては知識の少なさが不安になり,迷いをほぐそうと文献
を読んだり図書館通いをしたりしたそうです。それでも1つの解明が1つの疑問
を生み出し,あふれる資料の波にもまれ何度も挫折しそうになりながら,書き
上げるまでに2年を要しています。
波打ち際から順を追って深海へと,そこに住む生物や地形,人間の営みを描
いた下絵は襖28枚分にもなったそうです。緻密に描き込まれたキャラクターや
歴史的な事象の1つ1つは好奇心を呼び起こし,今,大人が読んでも十分に楽し
める内容です。加古氏の本を通じてどれだけの子供が科学に興味を持ってきた
でしょうか。素晴らしい仕事に改めて頭が下がる思いです。【杉】
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
光の求人サイト「オプトキャリア」【今週の募集案件】
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
■ 技術, 研究・開発 / 営業【勤務地:いずれも静岡県】
【仕事内容】
光学計測システム製品の開発,評価
カメラ・OIS・レンズメーカーなどに向けた光学システムの開発・設計・試作・
評価,AR/MRなどに向けたプラン開発
レーザー系営業, 光学系営業
カメラ・OIS・レンズメーカーおよびAR/MRなどに向けた光学システム開発チー
ムの営業技術
【必要能力】
仝学設計(Code-V,Zemax等を用いたレンズ設計・レーザ光学設計など)の実
務経験5年以上
英会話TOEIC 700点相当/光学計測システムなどの開発企画や営業技術経験5
年以上
【学歴】
き 共に大学卒以上
【想定年収】
500〜900万円 / 450〜900万円
(いずれも経験・能力・年齢・前職給を考慮し相談の上決定)
☆ マイカー通勤OK
☆ 遠方からの通勤や単身赴任などもサポート
詳細は下記よりお問い合わせください。
http://www.optocareer.com/contact.html?=180510
E-mail:optocareer@optronics.co.jp
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
OPTRONICS ONLINE 「オススメ記事/動画」
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
■白色パルス光源の強度雑音キャンセル法の開発と誘導ラマン分光イメージン
グへの応用(若手研究者の挑戦)
https://optronics-media.com/publication/20180501/51095/
試料に刺激(ポンプ)を与えて,その刺激を光(プローブ)の透過率変化で検
出する方法,ポンプ・プローブ法において,光源の強度揺らぎ(強度雑音)を
除去して信号雑音比(S/N)を向上させる方法について,東京理科大学助教の瀬
戸啓介氏に紹介して頂きました。誘導ラマン散乱の分光計測をしながら,強度
雑音を1/30まで削減できるという手法をご覧ください。
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【OPTRONICS Twitter/facebookのつぶやき】
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Twitter/facebookのオプトロニクス社アカウント
https://twitter.com/optronics
https://twitter.com/OPTOTV
https://www.facebook.com/optronics.co.jp
ここで紹介する以外の情報もいろいろ呟いています。上記のアカウントを是非
フォローしてください。
※【Webで注目の光技術】はネット上で見つけた話題です。ソースを確認し
ていませんので,内容についてはご自身で判断をお願いします。
【OPIE'18】
■昭和オプトロニクス,光の操作技術を提案
http://www.optronics-media.com/news/20180426/51013/
■ハイフィネス,新製品の線幅測定装置を展示
http://www.optronics-media.com/news/20180426/51010/
■マイクロビジョン,レーザープロジェクターの応用を提案
http://www.optronics-media.com/news/20180426/51009/
■NEDO,高出力フォトニック結晶レーザーを展示
http://www.optronics-media.com/news/20180426/51006/
【光技術】
■NICTら,光子と相互作用した人工原子の巨大光シフトを生成
http://www.optronics-media.com/news/20180508/51146/
■阪大ら,逆時空間における光と電子の接触と反発を観測
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51075/
■東大,平衡状態における量子もつれの空間分布を完全に決定
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51072/
■阪大,AIによる高分子太陽電池の材料設計に成功
http://www.optronics-media.com/news/20180509/51154/
■理研,有機薄膜太陽電池の分子レベルの混合状態を明らかに
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51039/
■京大ら,寿命1000倍となる有機太陽電池の構造を実現
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51077/
■理研,プラズモン共鳴による有害分子の分解を確認
http://www.optronics-media.com/news/20180507/51113/
■NTTら,PCFで加工用高出力レーザーの長距離伝送に成功
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51020/
■監視カメラ世界市場,2018年に5,700万台に
http://www.optronics-media.com/news/20180508/51141/
■2017年の世界半導体材料市場,前年比9.6%増に
http://www.optronics-media.com/news/20180502/51105/
■パナ社員,CD/DVDピックアップの開発で紫綬褒章を受章
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51017/
【医療・バイオ】
■理研,多光子レーザー顕微鏡向け球面収差補正システムを開発
http://www.optronics-media.com/news/20180508/51139/
■京大,光超音波トモグラフィで3D血管地図を作成
http://www.optronics-media.com/news/20180502/51098/
■理研,レーザーで超高感度マイクロ流体SERSセンサーを作製
http://www.optronics-media.com/news/20180502/51096/
■東大,細胞から臓器までpHを蛍光で簡便に計測
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51056/
■理研,生体を構成する原子のイオンの散乱因子を電顕と放射光で決定
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51034/
■市大,CO2と太陽光で発電するバイオ燃料電池を開発
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51041/
■NEC,虹彩認証技術の精度評価で1位
http://www.optronics-media.com/news/20180502/51100/
【新製品・開発品】
■世界初!光学素子評価用,全自動分光光度計
http://www.optronics-media.com/news/20180502/50752/
■光響,安価なファイバーレーザーマーカーキットを発売
http://www.optronics-media.com/news/20180509/51156/
■富士フイルム,画像強調機能搭載LED内視鏡システムを発売
http://www.optronics-media.com/news/20180508/51148/
■オクテック,超高輝度の自動運転室内検証システムを発売
http://www.optronics-media.com/news/20180502/51103/
■村田機械,薄板〜中厚板対応ファイバーレーザー加工機を発売
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51022/
【その他技術】
■東北大ら,長距離核スピン偏極の観測に成功
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51069/
■東大ら,2分子分の厚みの大面積有機半導体を開発
http://www.optronics-media.com/news/20180501/51052/
【Webで話題の光技術】
■LONGiが太陽光パネルで世界新,ハーフカット単結晶PERCで360W
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1805/09/news041.html
■有機太陽電池として最高レベルの変換効率15%を米ミシガン大学が達成
https://techable.jp/archives/76223
■光照射によってペロブスカイト材料中のイオン流が100倍に増大
https://news.mynavi.jp/article/20180507-626999/
■ほぼ地図不要の自律自動車システム,MITチームが開発
https://www.technologyreview.jp/nl/self-driving-cars-are-useless-without-specialized-maps-this-invention-could-free-them/
■トヨタ注目のスタートアップが開発した「新しいセンサー」の正体
https://wired.jp/2018/05/05/luminar-lidar-self-driving-cars/
■進化する“超LiDAR”,自動運転時代に生き残りを賭ける
http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00270/02/
■純銅加工も楽々,国産青色半導体レーザー
http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/nmc/18/00015/00002/
■工作機械メーカー,金型補修を複合加工機で競う
https://newswitch.jp/p/12739
■川底の地形もレーザーでお見通し
http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00268/042400002/
■新兵器続々デビュー! 新種のレーザー式固定オービスがまた大阪に出現!
https://motor-fan.jp/article/10004045
■防犯タグに応用可能なレーザーシール
https://www.natureasia.com/ja-jp/research/highlight/12488
■鉄道向けの曲がるLEDディスプレイ,成城学園前駅で実証
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1805/02/news013.html
■映写機のない上映システム「LEDシネマスクリーン」
http://realsound.jp/tech/2018/04/post-188549.html
■自動化ラインでLED照明の生産を行う アイリスオーヤマ
https://www.sankei.com/economy/news/180424/prl1804240413-n1.html
■英バーミンガム大学が低コストで効果的な色覚補正コンタクトレンズを開発
https://techable.jp/archives/76416
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
今週のコラム「スワイヤーアイ」
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
皆さんは昨年,太平洋・マリアナ海溝で新種の深海魚が撮影されたというニ
ュースを覚えていらっしゃるでしょうか。先日番組を観たところ,その後捕
獲されて生態が少しづつわかってきたようです。
その深海魚は,水深1万mの水圧にも耐えられる特殊容器の中に4Kカメラを取
り付けた超深海カメラシステムによって,マリアナ海溝の水深8,178m地点で
撮影されました。ちなみにその地点の水圧は800kg以上にもなるそうです。
そして研究チームは捕獲するために再びマリアナ海溝に向かい,水深7,581m
に罠を仕掛けて1匹だけ捕獲することに成功しました。撮影された時点では学名
はなく,マリアナスネイルフィッシュと呼ばれていましたが,その後「シュー
ドリパリス スワイヤーアイ」(以下,スワーヤーアイ」と名付けられました(
番組ではこのように紹介していましたが,WEBで調べると「シュードリパリス
スワイヤーアイ ゲリンジャー アンド リンレイ」でした)。
スワイヤーアイは,身体がうろこではなく透明なゼラチン質で覆われていま
す。そしてCTスキャンした画像を見ると,3重4重にもなる鋭い歯が並んだ口
の奥に咽頭顎がありました。撮影された映像ではエビを食べている様子が映っ
ていましたが,この顎によって固い甲殻類でも食すことが可能だとわかりまし
た。
そしてなぜ800kg以上の水圧がかかる場所で生き抜けるのか。通常の海の生物
は,高い水圧がかかると動きが止まってしまうそうです。それはカラダを作る
タンパク質に高い水圧がかかると水の分子がタンパク質の機能を止めてしまう
からだとか。
しかしスワイヤーアイは,これを防ぐためにTMAOという水分子を強力に引き
つける物質を体内に多く持っていることが判明。TMAOが水分子をタンパク質か
ら引き離すことで深海の高い水圧の中でも正常に働くのです。深い場所に住む
魚ほどこのTMAOが多く,スワイヤーアイは全ての魚のなかで最も多く持ってい
るようです。
さらに頭頂部に平衡感覚を司る耳石と呼ばれるものがありました。直径は
1mm程度のものですが,魚の一生を知る重要な手がかりになるとか。その耳石
をスライスして断面を観察してみると木の年輪のような輪が見え,この線一本一
本が1年と考えられ,この耳石の持ち主は9歳ということがわかりました。
そして耳石の成分を,酸素同位体に注目して調べてみると,その比率によっ
て耳石が作られた当時の海水温がわかるそうです。すると耳石の外側(9歳時
)はマリアナ海溝の深海と同じおよそ水温2℃だったのに対し,生まれてから2
〜3年は,成魚が生息している場所よりも5℃も水温が高い水深1,000m付近で成
長していたことがわかりました。
どうして赤ちゃんの時に水深の浅い場所にいるのか。深海から上がって来れ
たとしてもどのようにして再び深海に戻るのか。この謎も今後の研究で解明さ
れることでしょう。でもマリアナ海溝の深さはおよそ1万1,000m。今回スワイヤ
ーアイが撮影された地点よりさらに3,000m近くも深いのですから,まだまだ未
知の生物,居るにちがいありません。【愛】
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
オプトロニクス社の募集中セミナー一覧
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
■性能限界を突破へ! 注目の非従来型バイオイメージング
2018年5月29日(火)【5/18まで早割実施中】
http://www.optronics.co.jp/seminar/bi_01.php
■基礎から学ぶ「光学設計セミナー」(2018年度)
2018 6/13(水), 7/12(木), 8/2(木), 8/24(金), 9/7(金), 9/28(金) 全6回
※個別受講可能
http://www.optronics.co.jp/seminar/sekkei/index.php
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
【6月8日】JOEM技術講座「図解・光散乱入門 -自然現象から学ぶ-」
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
私たちが見慣れている青空がどのように色付くのか,皆さんはご存知ですか
。実は,空が色付く理由は古くからの謎でした。この謎を解明したのがイギリ
スの物理学者レイリー卿(1842年〜1919年)です。
彼は,地球大気中にある窒素や酸素などの気体分子が太陽の光を散乱して,
空が青くなることを突き止めました。気体分子など光の波長に比べて非常に
小さい物質が起こす散乱は,レイリー卿の発見にちなんで,「レイリー散乱
」と呼ばれています。
本講座は,散乱とは何なのか,散乱はどのように発生するのか,何故違う色
の散乱があるのかといった散乱現象の基本について,「光と原子のやり取り」
というミクロな視点から深く理解することを目的にしています。
非常に微小な粒子が光と出会うことにより生じる散乱は,最も基本的な光と
物質の出会いです。実は,透過,反射,屈折などの光学現象は,光と物質の出
会いによって発生した膨大な数の散乱が干渉して生まれるもので,光が多数決
をとった結果なのです。
本講座が終わる頃には,皆さんが別々のものとして学校で習った透過,反射
,屈折などが,結構似通った光学現象であることに気が付いて頂けることでし
ょう。
日時:2018年6月8日(金)13:00〜17:00
会場:機械振興会館 別館4階(港区芝公園)
講師:田所利康氏(有限会社 テクノ・シナジー 代表取締役)
内容:1.イントロダクション:自然界に見られる散乱
2.散乱の正体を探る
3.粒子サイズで変わる散乱のようす
4.粒子密度で変わる散乱のようす
5.散乱で生じる多彩な空の色
6.青空の偏光
7.まとめ
参加費:(テキスト代・消費税を含む)
正会員 20,520円 賛助会員 24,840円
協 賛 28,080円 一 般 31,320円
申込期限:2018年6月1日(金)まで
申込方法:ホームページから直接お申込み出来ます。
お申込みフォームは下記のURLからお入りください。
http://www.joem.or.jp/moushikomi.htm
問合せ先:一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
TEL:03-3435-9321 FAX:03-3435-9567
E-mail:info@joem.or.jp
----------------------------------------------------------------------
|
|