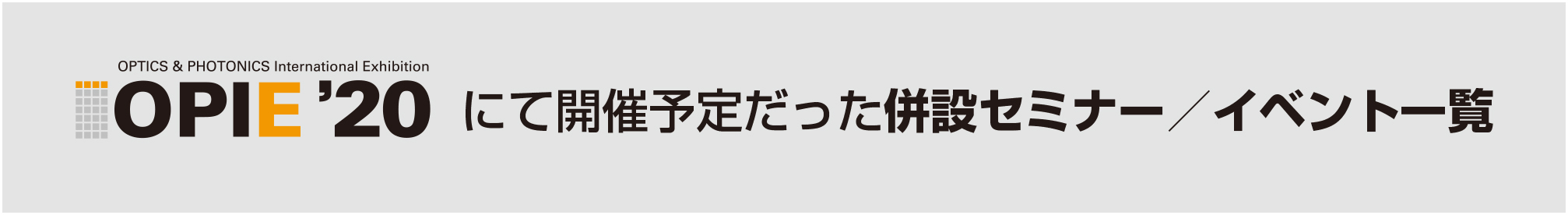宇宙・天文光学 特別技術セミナー
赤外線で見通す宇宙
<検討中>
宇宙インフレーションの痕跡を探る宇宙マイクロ波背景放射の偏光観測
静止地球観測と大型分割望遠鏡システムの研究開発
以上が動機的な背景であるが、一方で技術的な背景に目を向けると、これまでに打ち上げられた宇宙望遠鏡は可視域ではハッブルが最大であり、その口径は2.4mである。望遠鏡は大型になるほど主鏡と支持構造の重量が打ち上げの負担となるため、単純に口径をサイズアップしていくことは難しい。
このような課題に対し、JAXA研究開発部門では軽量な主鏡材料と分割鏡システムによって上述した静止地球観測衛星を実現すべく検討を進めている。本講演では、静止地球観測衛星構想について要素技術の概要を交えながらJAXAの取り組みを紹介する。
超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS)の運用成果
超低高度衛星のメリットは小さなセンサを用いて高分解能の衛星画像を取得できることですが、「超低高度」と呼ばれる軌道高度200~300kmでは通常の地球観測衛星が飛行する高度に比べて大気抵抗や衛星材料を劣化させる原子状酸素の密度が1000倍程度となります。このため、超低高度は、精密な姿勢・軌道制御や長期間の衛星運用が求められる地球観測衛星には不向きとされていました。
「つばめ」は、推力は極めて小さいものの推進効率の高いイオンエンジンを用いて、高度300km以下の超低高度域において軌道保持技術を実証するとともに、高分解能の衛星画像を取得する実験により、良好な画質の画像を取得しました。また、大気密度、原子状酸素の密度や大気に曝露した材料サンプルの劣化状況など、これまでにない長期間のデータを取得するとともに、JAXAが開発した材料が長期間の原子状酸素の曝露に耐えることも実証しました。 このようなイオンエンジンを用いた超低高度からの地球観測運用や原子状酸素対策に関する基盤的な技術・ノウハウを獲得したのは、JAXAが世界初となります。
本講演では、「つばめ」の軌道上運用で得られた成果と将来に向けた構想について紹介します。
大地を見つめる「だいち」の眼 ~先進光学衛星「だいち3号」の開発とデータ利用~
「だいち3号」の主要なミッションは、日本全域および全地球規模の陸域を高分解能かつ高頻度に観測し、蓄積した平時の画像や発災時の画像を防災・災害対策等を含む広義の安全保障に活用すること、また高精度な地理空間情報を整備・更新することである。このミッション要求に応えるため、「だいち3号」では新たに広域・高分解能センサ(WISH: WIde-Swath and High-resolution imager)を開発した。WISHは光学系の大型化・検出器の高感度化により、「だいち」と比較して広い観測幅(直下70km)を維持しつつ、約3倍高い地上分解能(直下0.8m)および可視・近赤外における観測バンド数の増加を実現している。
本講演では「だいち3号」のミッション、機能・性能、最新の開発状況を紹介するほか、様々な分野における衛星データの利活用についても具体的事例を交えて解説したい。
天の川の最新描像と赤外線位置天文観測衛星JASMINEで挑む天の川と巨大ブラックホールの謎
すばる望遠鏡と30m光学赤外線望遠鏡TMTが結ぶ新たな宇宙像


| お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) ●銀行振込 ※早割支払期日:4/24(金) |

|
セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/22までは受講料の50%、3/23以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。なお、欠席された場合、配布テキストをお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

佐藤 世智
宇宙航空研究開発機構
2005年 東京大学工学部卒業.2007年 東京大学大学院情報理工学系研究科卒業、同博士後期課程進学.2008~2010年 JST-CREST研究員(技術領域:先進的統合センシング).2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科修了 博士(情報理工学).計測分析機器メーカー勤務を経て2018年より現職.専門は光計測。計測自動制御学会会員。
此上 一也
宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門 SLATSプロジェクトチーム
1998年 東京工業大学工学部機械宇宙学科卒業
2006年 東京工業大学大学院理工学研究科機械宇宙システム専攻博士後期課程修了(博士(工学))
同年 宇宙航空研究開発機構入社。
2006~2008年 JAXA研究開発本部にて宇宙航空プロジェクト研究員として宇宙ロボティクスの研究に従事。
2008年より、JAXA第一宇宙技術部門にて、超低高度衛星技術試験機(SLATS)プロジェクトに携わり、衛星システム(姿勢制御系)およびミッションセンサ(光学センサ)を担当。
所属学会:日本航空宇宙学会
度會 英教
宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門 先進光学衛星プロジェクトチーム ファンクションマネージャ
名古屋大学理学研究科素粒子宇宙物理学専攻満了 博士(理学)
宇宙科学研究所COE研究員、日本学術振興会特別研究員として赤外線天文学の研究に従事したのち、2001年に宇宙開発事業団(当時)入社。陸域観測技術衛星「だいち」プロジェクトチームにおいて「だいち」搭載パンクロマチック立体視センサ(PRISM)および高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)の開発を担当。地球観測研究センター等を経て2016年4月より先進光学衛星プロジェクトチーム。広域・高分解能センサの開発と衛星データの利用推進業務を担当。
郷田 直輝
国立天文台
国立天文台JASMINEプロジェクト プロジェクト長・教授
京都大学理学部卒業。1989年、京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。京都大学理学部助手、大阪大学理学部助教授を経て、1999年に国立天文台教授に着任。現在、JASMINE プロジェクト長、東京大学大学院教授、総合研究大学院大学教授、 JAXA 宇宙科学研究所客員教授、鹿児島大学大学院客員教授を兼任。日本天文学会、国際天文学連合(IAU)、日本物理学会に所属。専門は宇宙論、銀河の形成・力学構造、重力多体系の非線形現象、位置天文学。現在、赤外線位置天文観測衛星である「JASMINE(ジャスミン)」計画を推進中。著書として『天の川銀河の地図をえがく』 (旬報社) 、『ダークマターとは何か』 (PHP研究所) 、『宇宙のことがだいたいわかる 通読できる宇宙用語集』(ベレ出版)等がある。
国立天文台
准教授
2003年 京都大学大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。
2004年 国立天文台上級研究員
2010年から2018年まで国立天文台ハワイ観測所ですばる望遠鏡の運用に携わる。
現在 国立天文台TMTプロジェクト准教授。