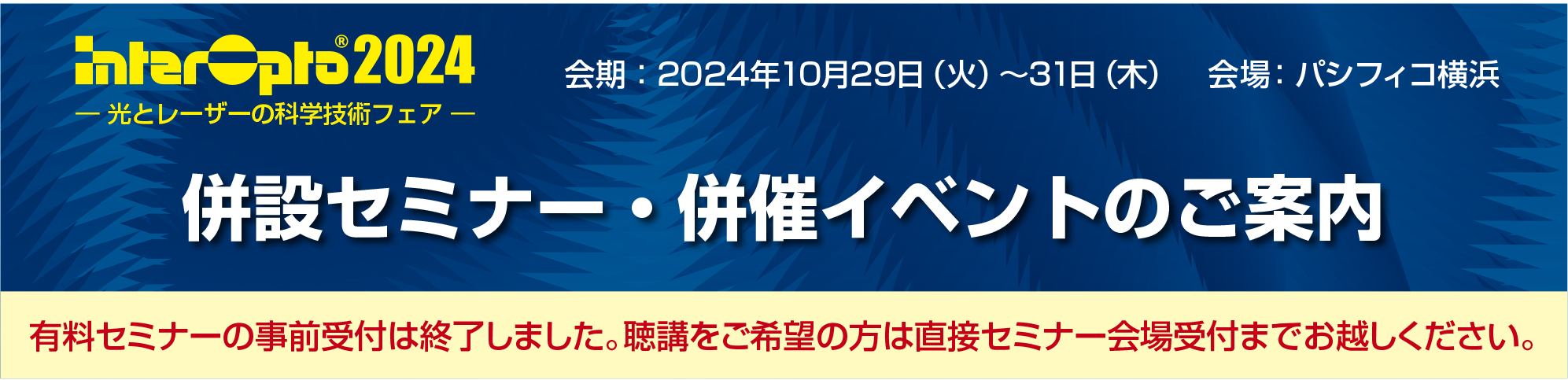紫外線セミナー
2024年10月29日(火)
10:30-13:00
アネックスホール F206
本セミナーでは、サファイア基板上に作製した高効率UV-C LEDの最新技術を説明し、加えてUV-C LEDを用いた除菌効果の実証とそのモジュール製品について紹介する。
【UV-1 】
短波長UVCLEDと応用の最前線
短波長UVCLEDと応用の最前線
(国研)理化学研究所 平山量子光素子研究室 主任研究員 平山 秀樹 氏
講演では、220~230nm帯LEDの高出力化の技術に関して、発光の高効率化、注入効率・光取り出し効率の向上に関して紹介し、また、230nm帯LEDを用いた高出力LEDモジュールと、それを用いたウイルス不活化実証試験などを紹介する。
除菌用UVCLEDの高効率・高出力化とその応用
豊田合成(株) ライフソリューション第1技術部 奥野 浩司 氏
UV-C LEDは、ウィルスや細菌を不活化することが出来る光デバイスであり、従来の水銀ランプの代替として早期の高効率・高出力化が期待されている。
弊社は液晶バックライト・照明分野で培ったInGaN系青色LED技術を活用し、AlGaN系UV-C LED及びその応用製品の開発に取り組んでいる。
一般的にLEDの効率は、内部量子効率、光取り出し効率、駆動効率の掛け算によって決まる。
これらの効率を高める為には、AlGaN結晶の高品質化と電気伝導の制御技術、加えてLED素子から光を取り出すための技術が求められる。
●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
窒化アルミニウム基板上に作成したFUV LEDの最近の進展と応用
旭化成(株) 研究・開発本部 先端技術研究所 次世代化合物半導体開発部 部長
國見 仁久 氏
國見 仁久 氏
水や空気中のウイルス・菌を不活性化する用途で広範に用いられている波長265 nmの紫外線発光ダイオード(Light Emitting Diode: LED)では、発光効率(電力変換効率)が5%を超える報告もなされており、その進展は著しい。その一方で波長が短くなるほど電力変換効率は著しく低下する傾向にあり、特に、波長240 nm以下の紫外線(Far Ultraviolet-C: FUV)LEDの電力変換効率は2023年には1%未満であったが、2024年には2.4%に達するまで向上した。
宇宙から地表に到達する紫外線は、オゾン層で吸収されるため、地表に届く光の波長290 nm以上に限定される。つまり、エネルギーに換算すると6 eV近い非常に大きなエネルギーを持つ波長230 nm付近のFUV光はこれまでの地球地表における自然界には存在しない光であり、小型かつ長寿命で高電力変換効率のFUV LEDを実現できれば、今後の様々な分野への応用展開の可能性を秘めている。
今回はFUV LEDの技術開発状況を主に紹介し、その応用展開についても述べる。
●入門程度(大学一般教養程度)
| 受講料(1セッション/税込) | |||
|---|---|---|---|
| 一般 | 主催・協賛団体会員/出展社/月刊オプトロニクス定期購読者 | 学生 | |
| ¥20,000 | ¥17,000 | ¥5,000 | |
お申込み受付は終了いたしました。
お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) |
 ※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|

※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、9/30までは受講料の50%、10/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

平山 秀樹
国立研究開発法人理化学研究所
平山量子光素子研究室 主任研究員
1994年 東京工業大学電子物理工学専攻博士課程修了(工学博士)
1994年 理化学研究所入所
2005年 テラヘルツ量子素子研究チーム、チームリーダー(現職)
2012年 平山量子光素子研究室、主任研究員(現職)
(兼務)埼玉大学連携教授、東京理科大学客員教授、徳島大学招聘教授
(公職歴) 応答物理学会理事(’21-22)、JJAP/APEX誌編集長(‘22)、NPO法人日本フォトニクス協議会理事・紫外線研究会委員長、NPO法人皮膚光線治療促進の会理事
奥野 浩司
豊田合成(株)
ライフソリューション第1技術部
2003年豊田合成株式会社入社, 青色LEDの製品開発に取り組む. 2014年名古屋大学大学院工学研究科電子情報システム専攻 博士(工学)取得を経て, 現在に至る. 窒化物半導体系の発光デバイスの研究開発に従事.
國見 仁久
旭化成(株)
研究・開発本部 先端技術研究所 次世代化合物半導体開発部 部長
2001年 旭化成株式会社 入社
以来、研究開発部門、事業部門において、シリコン半導体、GaAs化合物半導体、それぞれのプロセス技術開発、アプリケーション開発、事業開発に従事。近年では、欧州の海外子会社の現地法人社長を歴任。
2023年より現職である、研究開発本部 先端技術研究所 にてワイドバンドギャップ化合物半導体の素子開発および基板開発に従事。