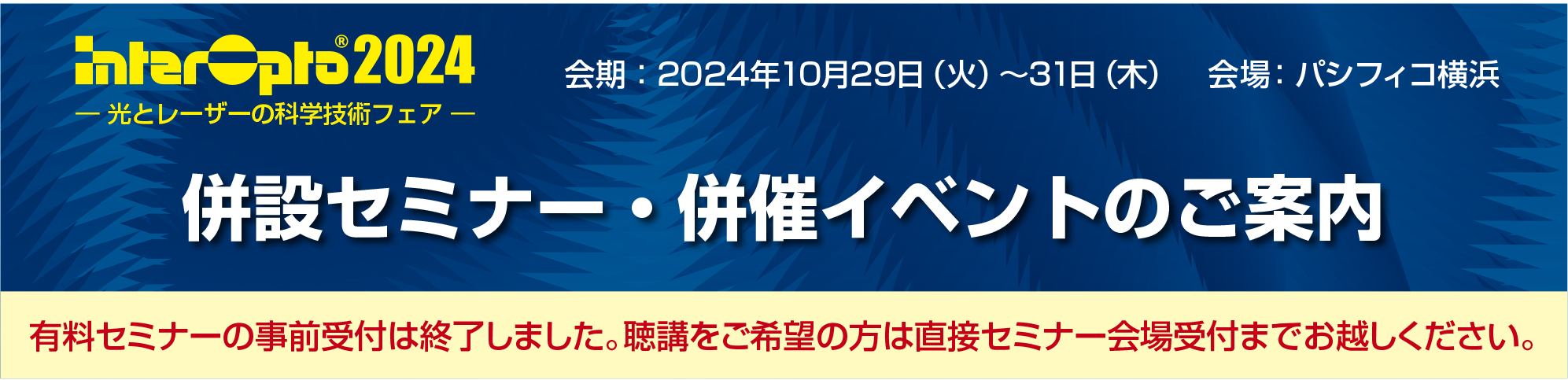分光セミナー
2024年10月31日(木)
10:30-13:00
アネックスホール F206
【SC-1 】
分子の大きさや濃度、および界面を探る分光法
和周波発生分光のチュートリアル
埼玉大学大学院 理工学研究科 教授 山口 祥一 氏
界面は、バルクでは見られない特異的な化学反応の起こる場であり、化学の様々な分野において重要な役割を果たしている。
大気環境のエアロゾル表面反応、液液界面での分離化学、固液界面の触媒反応、生体膜の選択的物質移動など、多様な実例をあげることができる。界面の化学を微視的に理解するためには、そこでの分子の構造とダイナミクスを精確に調べる方法が必要不可欠である。
そのための強力な実験手法として、和周波発生(SFG)分光法が知られている。SFGでは、角周波数ω1の可視光とω2の赤外光を界面に照射して、それらの和の角周波数ω1+ω2の和周波光を検出する。和周波光の電場は、二次非線形光学感受率(x(2))、入射するω1光の電場、ω2光の電場、の3つの量の積となる。
SFGの界面選択性は、x(2)が界面においてのみノンゼロ、バルクではゼロになることに由来している。和周波光は界面においてのみ発生するため、それを検出すれば自動的に界面を選択的に観測していることになる。x(2)に含まれる情報を読み解くことによって、界面の分子の構造とダイナミクスについての知見を得ることができる。
本講演では、SFGの原理、実装、応用例を紹介する。
●中級程度(大学院程度、ある程度の経験を有す)
蛍光相関分光法の基礎
(国研)理化学研究所 開拓研究本部 田原分子分光研究室 専任研究員 石井 邦彦 氏
蛍光相関分光法(Fluorescence Correlation Spectroscopy, FCS)は、蛍光の揺らぎを解析することで分子の大きさや濃度などの情報を得ることができる分光分析法である。
本講演ではまず、FCSの概要と歴史を紹介し、さらにその原理から実装までを説明する。蛍光計測を用いると一分子レベルの極めて高い感度を達成することができるが、FCSではこのことを利用して、水溶液中で1ミクロン以下の領域に分子がランダムに出入りする様子を観察する。このような実験を行うためには、蛍光プローブ、レーザー光源、共焦点顕微鏡、高感度な光検出器などの高度な光技術が必要とされ、また得られる信号の解析と理論的解釈にも専門的な知識を要する。
講演では、これらについてなるべく平易に説明するとともに、FCSのいくつかの応用例を紹介する。最後に発展的な話題として、複数の蛍光波長を用いた計測や蛍光寿命の情報を取り入れた計測など、研究レベルで活用されているFCSの比較的新しい手法を取り上げ、その概要を簡単に述べる。
●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
| 受講料(1セッション/税込) | |||
|---|---|---|---|
| 一般 | 主催・協賛団体会員/出展社/月刊オプトロニクス定期購読者 | 学生 | |
お申込み受付は終了いたしました。
お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) |
 ※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|

※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、9/30までは受講料の50%、10/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

山口 祥一
埼玉大学大学院 理工学研究科
教授
1990年 東京大学理学部物理学科卒業
1992年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻修士課程修了
1992年 財団法人神奈川科学技術アカデミー 研究員
1995年 東京大学大学院総合文化研究科 助手
1998年 三菱化学株式会社 副主任研究員
2002年 理化学研究所 専任研究員
2014年 埼玉大学大学院理工学研究科 教授
石井 邦彦
国立研究開発法人 理化学研究所
開拓研究本部 田原分子分光研究室 専任研究員
1997年東京大学理学部化学科卒業(指導教官:田隅三生教授)。2003年東京大学大学院理学系研究科化学専攻博士課程修了(指導教官:濵口宏夫教授)。2003年理化学研究所入所。2014年より理化学研究所田原分子分光研究室専任研究員。現在主に一分子蛍光計測を基盤とした新規計測手法の開発と生体分子ダイナミクスへの応用研究に携わる。