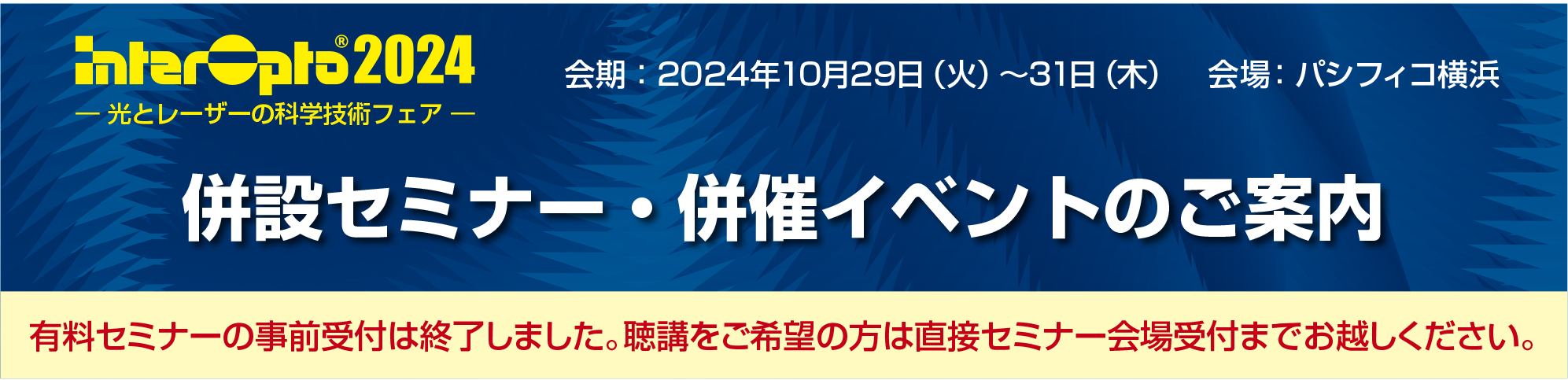レーザー安全セミナー
一般社団法人 レーザー学会
本セミナーは、厚生労働省・基発0325002号(平成17年3月25日付)「レーザー光線による障害防止対策要綱」に記載されている安全衛生教育の5項目を遵守してプログラムを構成しています。具体的には、レーザーの基礎とその応用、レーザーが人体へ与える影響、保護めがね・保護着衣、レーザー製品の安全基準の概要、レーザー安全対策の基礎と実際であり、レーザー安全に関する幅広い範囲を網羅しています。レーザー技術の進展および応用範囲の展開に合わせて、セミナー内容を更新しています。ただし、「レーザー製品の安全基準」の詳細については、セミナー内容の対象外となっています。 本セミナーは、主にレーザーを初めて取り扱う人を対象としています。既に取り扱っている人および教育・指導を担当している人にも有用な内容となっています。
※全講演を受講し、習熟度確認試験を受験して頂いた方には、レーザー学会より「受講証」が発行されます。
【開催日時】
●2024年10月31日(木)10:20~18:00(10:00開場)
【会場】
●パシフィコ横浜 アネックスホール
セミナーお申込み、詳細は下記のページをご確認ください
【聴講料】
● レーザー学会正会員:25,000円(税込)
● 非会員※ :35,000円(税込)
● 学生:10,000円(税込)
※ 賛助会員に所属する非会員の方を含みます。
開会挨拶と留意事項の説明
レーザーの基礎とその特徴
レーザー装置の仕組みとその応用
目に与える光・レーザーの影響と眼傷害事例
休憩・昼食
皮膚に与える光・レーザーの影響と皮膚傷害事例
光・レーザー用保護めがねと防護シールド
レーザー安全基準
光・レーザー安全対策の基礎
(2) 使用するレーザーの波長で十分な光学濃度を持った保護めがねを着用し、保護めがねを着用していてもビームを直接見ることは厳禁である。
(3) 反射、散乱光も目に入らないように注意し、腕時計、指輪など光を反射しそうなものは外す。
(4) 可能な限り明るい環境で作業し、視線とビームの高さが一致しないようにする。
(5) レーザーの光路およびその延長上には立たないようにする。光路の延長上では何かの拍子にミラー等がずれたり倒れたりすると、自分にレーザー光が当たる恐れがある。
(6) レーザービームの終端は拡散反射体または吸収体(パワーメータなど)で遮蔽する。
(7) レーザーの調整や、光路の調整を行う場合には、レーザーの出力やパルスの繰り返しを可能な限り低くして行う。
(8) レーザービームに直接皮膚をさらさないようにする。衣服は皮膚の露出の少ない難燃性の素材のものが良い。
(9) 半導体レーザーを除くほとんどのレーザーでは内部に高圧電源があり感電の危険性が高いので、筐体を開ける作業は教員や管理責任者の立ち合いのもとでのみ行う。
(10) レーザー照射で発生する有害物質、またはレーザー内部やレンズ等の光学部品で使用されている有害物質にも注意を払う。
休憩
光・レーザー安全対策の実際(一般消費者)
光・レーザー安全対策の実際(教育・研究機関)
光・レーザー安全対策の実際(産業分野)
休憩
習熟度確認試験(10問)
解答用紙の回収と受講証の配布
お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) |
 ※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|

※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、9/30までは受講料の50%、10/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

鈴木 将之
同志社大学
理工学部電子工学科 教授
同志社大学理工学部電子工学科教授,博士(工学).1998年近畿大学理工学部電気工学卒業,2003年大阪大学大学院工学研究科電子情報エネルギー工学専攻博士後期課程修了,博士(工学).2003年4月東京大学物性研究所先端分光研究部門学術研究支援員,2008年4月日本原子力研究開発機構光医療産業連携センター 任期付研究員,2011 年7 月埼玉医科大学医学部眼科先端レーザー医学研究センター准教授,2016 年10 月愛知医科大学医学部寄付研究部門准教授,2019 年4 月同志社大学理工学部電気工学科准教授,2023年4月より現職.高性能ファイバレーザー開発とこれを光源とした生体分光の研究を進めてきた.近年は,モード同期ファイバレーザーを光源とした時間伸長分光による生体イメージングに関する研究に着手している.レーザー学会,応用物理学会,日本光学会,電子情報通信学会,米国光学会,等会員.
近江 雅人
大阪大学大学院
医学系研究科保健学専攻 教授、博士(工学)
平成2年:福井大学工学部電気工学科卒業、平成7年:大阪大学大学院工学研究科電磁エネルギー工学専攻・博士課程修了、同年大阪大学医学部保健学科医用工学講座助手、平成19年:同大学大学院医学系研究科医用物理工学講座助教(学内講師)、平成24年より現職。 レーザー学会、応用物理学会、日本光学会、日本レーザー医学会、日本生体医工学会、日本発汗学会各正会員。平成22年レーザー学会進歩賞受賞。 レーザー学会・研究委員会・委員(レーザー医学・生物学応用担当)および「レーザー安全セミナー」実行委員会・委員、日本レーザー医学会・評議員ならびに安全教育委員会・委員、日本光学会・生体医用光学グループ・庶務幹事。
中西 孝子
昭和大学
キャリア支援室 准教授
1981年 3月昭和大学薬学部卒業
1984年 1月昭和大学医学部第二薬理学教室助手
1993年 State University of New York at Buffaloに留学
1998年 12月昭和大学医学部第二薬理学教室講師
2008年 4月 昭和大学医学部第二薬理学教室准教授
2011年 4月 昭和大学医学部生理学講座准教授
2017年 4月 昭和大学キャリア支援室准教授 現在に至る
1994年から日本薬理学会評議員、 2002年から日本眼薬理学会評議員、2004年から日本酸化ストレス学会評議員。2014年から日本生理学会評議員、1997年一般財団法人 光産業技術振興協会[Lプロジェクト総合委員会]委員、1998年から2000年 即効型国際標準創生研究総合委員、1998年から1999年 IEC/TC76国内対策委員会(レーザー安全)、 2004年から2005年 一般財団法人日本規格協会「色再現管理標準化」委員、2011年から2014年 一般社団法人レーザー学会「レーザー安全教育システム」専門委員会委員、2015年から2020年 光・レーザー安全技術専門委員会委員、2021年から現在 レーザー安全セミナー実行委員会委員。
河野 太郎
東海大学
医学部外科学系形成外科学 教授
東京女子医科大学形成外科研修(1993.4-1995.3)
東京都立 多摩総合医療センター外科研修(1995.4-1997.3)
東京女子医科大学形成外科 助教(1997.4-2007.3)
東京女子医科大学形成外科 准講師(2008.4-2013.3)
東海大学医学部外科学系形成外科学 准教授(2013.4-2021.3)
日本大学医学部形成外科学系形成外科学分野 客員教授(2016.1-)
東海大学医学部外科学系形成外科学 教授(2021.4-)
日本臨床皮膚外科学会 理事長
日本レーザー医学会 理事・安全教育委員会委員
日本血管腫血管奇形学会 理事・監事
日本美容外科学会 理事
日本アートメイク学会 理事
日本形成外科学会 評議員
日本美容皮膚科学会 評議員
加尻 慎也
山本光学(株)
開発部ビジョンケア・光研究所 所長
2001年3月、甲南大学大学院自然科学研究科卒
2001年4月、山本光学株式会社入社
2017年4月、同開発部技術開発課 課長
2021年4月、同開発部ビジョンケア・光研究所 所長、現在に至る。
レーザー保護具の開発、遮光保護具、保護めがねに関する研究開発に従事。
・ IEC TC76レーザ安全性標準化部会委員
・ ISO TC94 SC6国内対策委員会委員
・ レーザ機器取扱技術者(第一種)
橋新 裕一
オフィス橋新
代表
近畿大学理工学部・元教授、博士(工学)。
1982年3月、近畿大学大学院博士後期課程、満期退学。同年4月近畿大学理工学部助手、1998年専任講師、2003年助教授、2007年准教授、2012年教授、2021年定年退職後、非常勤講師、2023年オフィス橋新・代表、現在に至る。
レーザー学会(フェロー・上級会員、レーザー安全セミナー実行委員会・委員長),日本レーザー医学会(名誉理事、安全教育委員会・委員),光産業技術振興協会(IEC/TC76レーザ安全性標準化部会・議長、ISO/TC172/SC9国内対策委員会・委員)、医療機器センター・委員、神戸健康大学・理事
2002年日本レーザー医学会総会賞、2009年国際レーザー医学・医療学会Good Speech Award、2013年IEC1906賞、2019年日本レーザー医学会査読賞、2021年レーザー学会フェロー
間 久直
大阪大学
大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 准教授
大阪大学 大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻・准教授、博士(工学)。 平成8年:静岡大学 工学部 光電機械工学科卒業、平成10年:東京理科大学 大学院理工学研究科 電気工学専攻 修士課程修了、平成13年:東京理科大学 大学院理工学研究科 電気工学専攻 博士後期課程修了、同年:川崎重工業株式会社 技術研究所入社、平成18年:大阪大学 大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 特任研究員、平成21年:同研究科附属高度人材育成センター 助教、平成26年:同研究科 環境・エネルギー工学専攻 講師、平成27年より現職。レーザー学会、電気学会、応用物理学会、日本レーザー医学会、日本レーザー歯学会、日本歯科用レーザー・ライト学会、日本光線力学学会、日本レーザー治療学会、日本質量分析学会、American Society for Mass Spectrometry各会員。レーザー学会 レーザー安全セミナー実行委員会 委員、日本レーザー医学会 評議員、安全教育委員会 委員、編集委員会 委員、日本レーザー歯学会 代議員、日本レーザー治療学会 評議員。
橋新 裕一
オフィス橋新
代表
近畿大学理工学部・元教授、博士(工学)。
1982年3月、近畿大学大学院博士後期課程、満期退学。同年4月近畿大学理工学部助手、1998年専任講師、2003年助教授、2007年准教授、2012年教授、2021年定年退職後、非常勤講師、2023年オフィス橋新・代表、現在に至る。
レーザー学会(フェロー・上級会員、レーザー安全セミナー実行委員会・委員長),日本レーザー医学会(名誉理事、安全教育委員会・委員),光産業技術振興協会(IEC/TC76レーザ安全性標準化部会・議長、ISO/TC172/SC9国内対策委員会・委員)、医療機器センター・委員、神戸健康大学・理事
2002年日本レーザー医学会総会賞、2009年国際レーザー医学・医療学会Good Speech Award、2013年IEC1906賞、2019年日本レーザー医学会査読賞、2021年レーザー学会フェロー
吉田 実
近畿大学
理工学部電気電子通信工学科 教授
1985年大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了、1985~2003年三菱電線工業(株)、2004年~近畿大学理工学部教授。現在、光産業技術振興協会光増幅器及びダイナミックモジュール標準化部会委員。電気学会電子材料技術委員会副委員長。2023年までNEDO事後評価分科会分科会長など。科学技術庁長官注目発明選定、近畿地方発明表彰、レーザー学会奨励賞、レーザー学会論文賞ほか。電気学会会員、レーザー加工学会会員、レーザー学会上級会員。現在の研究課題として波長1 µmあるいは1.55 µm帯を中心に、光ファイバ増幅器、シングルモードファイバ出力キロワット級パルスファイバレーザー、フェムト秒パルスレーザー、ノイズライクパルスレーザー、480から2200nmにわたるファイバ出力高安定広帯域光源、レーザー出力のコヒーレント加算、光ファイバ計測などの開発を進めている。
橋新 裕一
オフィス橋新
代表
近畿大学理工学部・元教授、博士(工学)。
1982年3月、近畿大学大学院博士後期課程、満期退学。同年4月近畿大学理工学部助手、1998年専任講師、2003年助教授、2007年准教授、2012年教授、2021年定年退職後、非常勤講師、2023年オフィス橋新・代表、現在に至る。
レーザー学会(フェロー・上級会員、レーザー安全セミナー実行委員会・委員長),日本レーザー医学会(名誉理事、安全教育委員会・委員),光産業技術振興協会(IEC/TC76レーザ安全性標準化部会・議長、ISO/TC172/SC9国内対策委員会・委員)、医療機器センター・委員、神戸健康大学・理事
2002年日本レーザー医学会総会賞、2009年国際レーザー医学・医療学会Good Speech Award、2013年IEC1906賞、2019年日本レーザー医学会査読賞、2021年レーザー学会フェロー