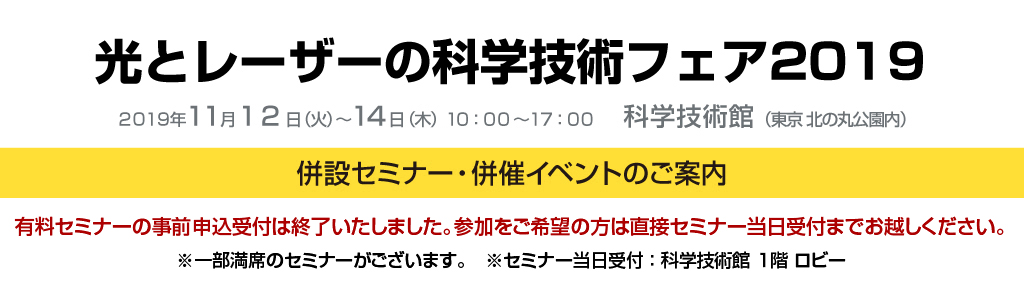空飛ぶクルマと未来ものづくりセミナー
■ 聴講無料 ■
空飛ぶクルマの実現に向けて
次世代モビリティへの光無線給電の可能性
多様な無線給電方式の中で、光ビームを用いる光無線給電は、遠隔給電可能、電磁ノイズ影響が無い、小型軽量などの利点から注目が集まり始めている。ただし、光無線給電は、現時点で実用段階に到達しておらず、モビリティへの給電可能性もほとんど議論されていない。本講演では、モビリティへの光無線給電適用の技術ポテンシャル・技術課題と適用シナリオを、デバイス技術・特性、システム機能・性能、周辺技術・要件の面から、講演者らの成果を含む光無線給電の検討事例も含めて議論する。また、移動・稼働機構など、モビリティ関連機構への適用も合わせて議論する。
レーザーが拓く照明・ディスプレイの未来
ここでは、レーザー照明およびディスプレイについて、まずその現状と課題を解説する。それを踏まえて、次の展開として期待されているIoT照明などに焦点を当てるとともに、照明・ディスプレイの未来における可能性を示す。
光が結ぶロボットと人間の協働社会
3Dプリンターと未来ものづくり
昨年発足したやわらか3D共創コンソーシアムが目指す「未来ものづくり」へつながる研究の最前線の事例として、ソフトマターロボティクスや食の転送プロジェクトなども紹介する。

| お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) ●銀行振込 |

|
セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、10/15までは受講料の50%、10/16以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
※新税率に関しまして:
2019年10月以降のイベントにつきましては消費税率10%でご請求させていただきます。

中野 冠
慶應義塾大学
大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
2008年4月より現在に至る:慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科,教授
2013年:スイス連邦工科大学訪問教授
1997年3月:名古屋工業大学博士課程工学研究科修了(在職)
1980年4月-2008年3月:株式会社 豊田中央研究所
1980年3月:京都大学 修士課程 工学研究科修了
博士(工学)
宮本 智之
東京工業大学
科学技術創成研究院 准教授
1996年 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 博士課程修了
1996年 東京工業大学 精密工学研究所 助手
1998年 東京工業大学 量子効果エレクトロニクス研究センター 講師
2000年 東京工業大学 精密工学研究所 准教授
2004年~2006年 文部科学省 研究振興局基礎基盤研究課材料開発推進室 学術調査官(兼務)
2016年東京工業大学科学技術創成研究院未来産業技術研究所 准教授
現在に至る
山本 和久
大阪大学
レーザー科学研究所 教授
1981年大阪大学基礎工学部電気工学科卒、同年松下電器産業(株)に入社。光導波路デバイス、光ディスク用青色SHGレーザー、映像・メディア機器へのレーザー応用(光メモリ、レーザーディスプレイ)などの研究に従事。
2009年大阪大学光科学センター 副センター長、特任教授。
2018年よりレーザー科学研究所 教授。
研究分野はレーザーディスプレイ・照明など。
・レーザー学会常務理事
・NPO法人日本フォトニクス協議会理事
・可視光半導体レーザー応用コンソーシアム代表
村井 健介
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
関西センター産学官連携推進室 連携主幹
1994年大阪大学大学院工学研究科博士課程修了、博士(工学)。1995年大阪工業技術研究所、2001年産業技術総合研究所に改組後現在に至る。2007〜2008年内閣府総合科学技術会議事務局(情報通信担当)、2017〜2018年近畿経済産業局地域経済部次世代産業・情報政策課 産業技術統括調査官。専門分野は、光と物質の相互作用(特にプラズモニクス)、ロボット技術と光技術の融合(ロボットフォトニクス)。Daiwa Awards(大和日英基金)、高温学会技術奨励賞などを受賞。レーザー学会、日本ロボット学会、米国物理学会に所属。レーザー学会ロボットフォトニクス専門委員会(主査)。
古川 英光
山形大学
教授、学部長特別補佐(研究)
東京都大田区出身。1996年3月東京工業大学大学院博士課程修了。博士(理学)。96年から2002年まで東京工業大学および2004まで東京農工大学にて高分子工学科で助手。2004年から2009年まで北海道大学院理学研究科にて准教授を経て、2009年より山形大学機械システム工学にて准教授に着任、2012年に教授に昇格。現在に至る。東京工業大学大学院生時代から一貫してゲルの研究に従事。その間、ソフト&ウェットマター工学研究室(SWEL)や、ゲルロボティクス研究としてソフトマターロボティクスコンソーシアムを立ち上げ、高強度ゲル材料の3Dプリンターを世界で初めて開発し、機械工学分野における新しい材料加工技術の発展に貢献。2012年には3Dプリンターブームで一躍注目を集め、2013年に山形大学ライフ・3Dプリンタ創成センター(LPIC)を発足(センター長)。3Dプリンターの技術を基に、2016年大学発ベンチャーとして株式会社ディライトマターを設立(共同設立者、現特別技術アドバイザー)。また、2018年にやわらか3D共創コンソーシアムを設立(会長)し、3Dプリンター技術の普及のため企業との共創の場(共同研究および勉強会)を提案し活動している。現在、山形大学工学部学部長特別補佐(研究担当)、文部科学省科学技術政策研究所科学技術予測センター(NISTEP)委員、高分子学会第34期業務執行理事、日米先端工学シンポジウム(JAFOE)運営委員長。所属学会・団体は、日本機械学会、米国機械学会(ASME)、SPIE、アメリカ電気化学会(ECS)、日本物理学会、日本化学会、米国化学会(ACS)、日本レオロジー学会、セルロース学会、日本ゴム協会、日本トライボロジー学会、やまがたメイカーズネットワーク(YMN)、先端錯体工学研究会、日本ロボット学会。また委員等は、日本工学アカデミー会員(現在、若手部会委員、未来の製造業プロジェクト委員)、鶴岡工業高等専門学校客員教授、米国サンティエゴ州立大学客員教授(2017.8まで)、日本バイオレオロジー学会理事、日本眼光学学会理事、アメリカ電気化学会(ECS)主催「第1回4Dマテリアル・システム国際会議(4DMS2018)」運営委員長。受賞歴としては、2010年に走査型顕微光散乱(SMILS)を活用した高分子ゲルの構造解析で(財)科学計測振興会より科学計測振興会賞を受賞。2013年にナイスステップな研究者として文部科学省科学技術・学術政策研究所より産学連携で世界最先端のゲル材3Dプリンターの開発の取り組みをしているとして表彰を受け文部科学大臣から授与、2017年日米先端工学(JAFOE)シンポジウムBest Speakers Award2016などを受賞している。