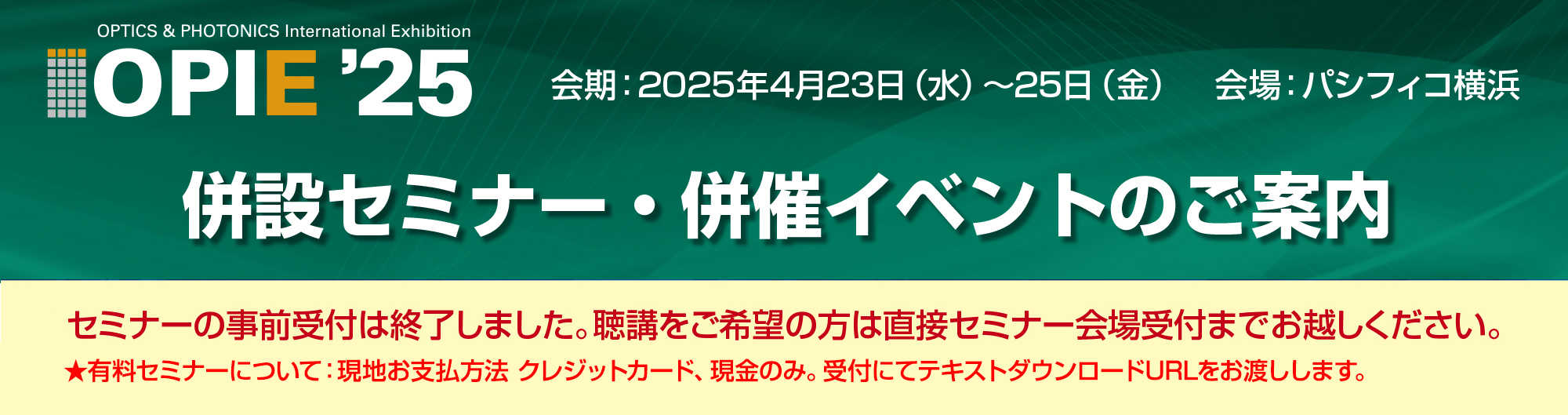赤外線技術セミナー
赤外線入門
本講演では,赤外線の科学・技術を理解するための基礎を説明します。
1.現代物理学における赤外線―赤外線とは何か、その性質と利用
2.赤外線放射の測定の物理量―何を測定しているか、主要な測定量
3.温度・熱と赤外線-物体の温度・熱と放射の温度・熱
赤外コヒーレント光源の最前線 -LD、QCLから様々な非線形結晶まで-
レーザー技術は現在、ノーベル物理学賞の受賞研究にも多大な影響を与えており、特に2018年には、超短パルスレーザー技術に対する貢献が評価され、ノーベル物理学賞を受賞した。この業績は、レーザー技術の発展における革新的なマイルストーンとなり、現在でも高強度レーザーの生成に広く利用されている。さらに、2023年には、アト秒パルス生成技術に関する研究がノーベル物理学賞を受賞し、極めて短い時間スケールでの電子の挙動の探査が新たな研究領域を切り開いている。
本講演では、そのような先端の産業・科学を支えるコヒーレント光源の、特に赤外領域での最前線について、レーザーダイオード(LD)や量子カスケードレーザー(QCL)といった光源を含め、固体・ファイバーレーザー、非線形光学を活用した波長変換やパルス生成技術まで、レーザー物理パラメーターの特異性や可変性を生かした応用例や最新の研究成果を解説する。
赤外線イメージング技術
| 受講料(1セッション/税込) | |||
|---|---|---|---|
| 一般 | 主催・協賛団体会員/出展社/月刊オプトロニクス定期購読者 | 学生 | |
| ¥20,000 | ¥17,000 | ¥5,000 | |
メタマテリアルと赤外線センシング技術
赤外透過材料 - 焼結法による赤外透過多結晶セラミックスの創製 -
赤外レンズ - 設計と活用
赤外線の領域には、さまざまな分子のスペクトルが存在し物質の異なった特性を見ることができる反面、その特徴から透過する材料が限られる。
レンズ設計においては、材料の特性や色収差の問題のため近赤外、中間赤外、遠赤外それぞれの領域で使える材料などについて理解をすることが必要となる。
本公演では赤外線用カメラの活用について紹介するとともに,赤外線用レンズの材料の特徴を比較,それらを使用した光学設計について解説を行う。
| 受講料(1セッション/税込) | |||
|---|---|---|---|
| 一般 | 主催・協賛団体会員/出展社/月刊オプトロニクス定期購読者 | 学生 | |
| ¥20,000 | ¥17,000 | ¥5,000 | |
防衛分野における赤外線技術
中赤外光を用いたヘルスケアモニタリング
中赤外光を用いた分光法により、生体を構成するタンパク質、脂質、糖質などの高精度な分析が可能になる。この領域では最近、中赤外量子カスケードレーザや、室温動作の半導体検出器が登場し、小型かつ安価なヘルスケア機器の実現性が高まってきておおり、新しいアプリケーションの発現が期待されている。
そこで本講演では、中赤外減衰全反射(ATR)法に基づく血中コレステロール分析、さらにはATR法に代わる光熱変換分光法として、光音響分光法、光熱偏向分光法などの血中成分分析への応用例などについて報告するとともに、中赤外光を用いたヘルスケア機器の今後の展望などについて述べる。
LiDARとLidarの原理と応用 ―地上から宇宙まで―
| 受講料(1セッション/税込) | |||
|---|---|---|---|
| 一般 | 主催・協賛団体会員/出展社/月刊オプトロニクス定期購読者 | 学生 | |
| ¥20,000 | ¥17,000 | ¥5,000 | |
|
本セミナーに関する お問い合わせ seminar@optronics.co.jp 件名に【OPIE25】と 記載下さい |
| お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) |
 ※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|

※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/31までは受講料の50%、4/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

廣本 宣久
静岡大学
名誉教授
1985年京都大学理学博士。
1984年より郵政省電波研究所,郵政省通信総合研究所(現国立研究開発法人情報通信研究機構)にて赤外・テラヘルツ工学の研究に従事。
2001年独立行政法人通信総合研究所関西先端研究センター長。
2003年総務省情報通信政策局技術政策課企画官。
2005年国立大学法人静岡大学工学部教授。
2020年静岡大学名誉教授。現在に至る
宮田 憲太郎
(国研)理化学研究所
研究員
2008年 マックスボルン研究所 客員研究員
2009年 マックスボルン研究所 博士研究員
2010年 メガオプト 研究員
2012年 メガオプト グループ長
2016年 メガオプト プロジェクトリーダー
2018年 理化学研究所 研究員
国際学会プログラム委員:
・ SPIE Photonics West LASE
・ OPTICA ASSL (Advanced Solid State Lasers)
・ OPIC ALPS (Advanced Lasers and Photon Sources)
田中 拓男
(国研)理化学研究所
チームリーダー/主任研究員
1968年3月28日生.1991年大阪大学工学部応用物理学科卒業,1996年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士後期課程修了,博士(工学),1996年大阪大学基礎工学部電気工学科助手,1997年大阪大学大学院基礎工学研究科助手,2003年理化学研究所 研究員,阪大フロンティア研究機構 特任助教授,2005年理化学研究所 先任研究員,2008年理化学研究所 准主任研究員,2010年北海道大学電子科学研究所 客員教授,2010年埼玉大学 連携教授,2012年学習院大学 講師,2014年理化学研究所 チームリーダー(兼務),2014年東京工業大学 連携教授,2017年理化学研究所 主任研究員,2017年台湾国立清華大学 客員教授,2019年フィリピン大学ディリマン校 客員教授,2020年台湾国立中興大学 客座教授
森田 孝治
(国研)物質・材料研究機構
電子・光機能材料研究センター 多結晶光学材料グループ
グループリーダー
1997年九州大学大学院総理工材料開発工学博士後期課程修了,博士(工学).1996年-1997年日本学術振興会特別研究員,1997年4月金属材料技術研究所(現:物質・材料研究機構)研究員、2010年-2012年ダルムシュタット工科大学客員研究員を経て、2022年4月より現職.セラミックスの超塑性・高温変形、放電プラズマ焼結(SPS)装置を利用した構造/機能セラミックスの創製と特性評価に関する研究に従事. 2001年日本金属学会奨励賞,2007年文部科学大臣表彰,2013年日本金属学会功績賞などを受賞.日本金属学会、日本セラミックス協会、粉体粉末冶金協会、各会員.
安藤 稔
(株)タムロン
光学開発センター センター長
2003年 3月 名古屋大学大学院素粒子宇宙物理学専攻博士課程後期修了
博士(理学)取得 赤外線天文学
2003年8月 株式会社 タムロン入社
デジタルカメラ用レンズ,リアプロジェクター用レンズ,監視カメラ用レンズ,車載用レンズ,赤外線レンズなどを担当
2014年3月 本部長代理
2015年4月 本部長
2022年1月~ 光学開発センター センター長
工藤 順一
防衛装備庁
新世代装備研究所 飯岡支所長
1995年筑波大学大学院理工学研究科修了。1995年より防衛庁技術研究本部第2研究所(現防衛装備庁新世代装備研究所)にて、光波センサシステム、赤外線撮像装置等の研究開発に従事。2016年4月同庁電子装備研究所センサ研究部光波センサ研究室長、2024年4月より現職。工学博士。
松浦 祐司
東北大学
大学院医工学研究科 教授
1988年東北大学工学部通信工学科卒,1992年東北大学大学院工学研究科修了,博士(工学).1993年住友電気工業横浜研究所研究員,1994年米国ラトガース大学セラミック工学科研究員として勤務の後,1996年東北大学大学院工学研究科助教授.2008年東北大学大学院医工学研究科教授.X線から遠赤外にわたる電磁波伝送路とその医療応用に関する研究に従事.レーザー学会,電子情報通信学会,応用物理学会,電気学会、SPIE会員.平成17年度文部科学省若手科学者賞受賞.レーザー学会東北・北海道支部長.レーザー学会フェロー
椎名 達雄
千葉大学
大学院工学研究院 准教授
1998.3 東京理科大学 理工学研究科 博士後期課程修了 博士(工学)
1998.4 和歌山大学 システム工学部 助手
2003.8 千葉大学 工学部 助手
2008.2 千葉大学 大学院工学研究院 准教授
現在に至る。
大気用ライダー、産業用OCT、並びに高散乱体中の光伝搬に関する研究に従事。