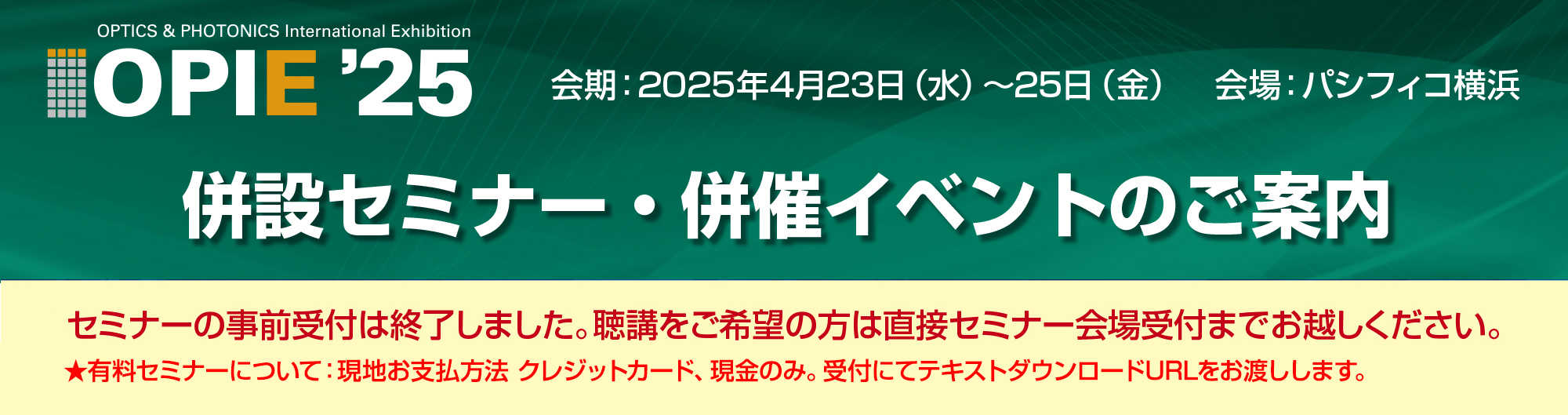紫外線技術セミナー
2025年04月23日(水)
13:40-16:35
アネックスホール F204
【UV-1 】
紫外線の基礎と応用
紫外線入門 光源からアプリケーションまで
(国研)理化学研究所 和田 智之 氏
生体無害ウイルス不活化220-230nm Far-UVC LEDの最近の進展
(国研)理化学研究所 平山 秀樹 氏
殺菌・ウイルス不活化用の光源として深紫外線が期待されている。
230nm、270nm帯の深紫外LEDは、殺菌・ウイルス不活化、浄水、空気浄化の作用に優れ、ウイルス感染拡大の防止、除菌用の光源として期待される。特に波長が230nmより短波長の紫外線は、人体の皮膚や目の最表面で吸収され内部の細胞に影響を及ぼさない事から、生体に安全で人の活動する空間での殺菌・ウイルス不活化が可能である。
人に安全で殺菌効果が強い230nm帯Far-UVC LEDはその応用範囲も拡大すると考えられ、注目が集まっている。最近の開発で230nm帯LEDの高効率化が盛んに行われており、その飛躍的な高出力化が実現している。
今回の講演では、220~230nm帯LEDの高効率化開発の最近の進展を紹介し、また、230nm帯LEDを用いた高出力LEDモジュールの進展と、それを用いたウイルス不活化実証試験などを紹介する。
●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
バイオレットライトの医療応用
(株)坪田ラボ 清原 和裕 氏
株式会社坪田ラボは、「VISIONary INNOVATIONで未来をごきげんにする」というミッションを掲げ、革新的な医療機器、医薬品の開発を目指している。特に、太陽光に含まれる波長360~400 nmの光であるバイオレットライトで活性化されるOPN5(非視覚型光受容体)が近視の抑制にとって重要であるという知見を基に、治療困難であった種々の眼科疾患及び脳機能疾患の治療の事業化を行っている。
眼科領域では、バイオレットライト照射による近視進行の抑制作用が見出され、現在はメガネ型バイオレットライト照射機器による近視進行抑制の検証的な臨床試験が進行中である。さらに、バイオレットライトによるOPN5の活性化が脳へ作用する事が明らかとなりつつあり、バイオレットライトの脳中枢領域への治療応用を志向した研究開発活動を行っている。
さらに当社のメガネ型バイオレットライト照射機器を用いた臨床試験・臨床研究では、その高い安全性も示されつつあり、安全性と有効性を兼ね備えた医療機器としての医療応用が期待される。
本セミナーでは、バイオレットライトの生体への作用についての内容を中心に、紫外領域に近い短波長光のみならず、その他の波長領域の光の生体への影響も併せてレビューする事で、生体にとっての光の重要性を再認識する機会としたい。
●入門程度(大学一般教養程度)
併催イベント一覧へ
2025年04月24日(木)
13:40-16:35
アネックスホール F204
【UV-2 】
紫外線の半導体製造技術
EUVリソグラフィ応用にむけた光源開発の現状
九州大学/ EUVフォトン社 溝口 計 氏
波長13.5 nmのEUV光は反射光学系(反射率68%程度)による縮小投影を用いたリソグラフィで1986年にNTTの木下ら4)により提唱された日本発の技術である。だが現在は世界の EUV リソグラフィの最先端量産用露光装置開発はオランダの ASML 社主導のもとに進んでいる。
近年光源の出力改善が進み、2017 年に発売された ASML 社の NXE-3400 において 250 W(設計値)を達成し、現在は500Wを超え、スループットは 125 WPH を超えた。Apple 社の iPhoneには台湾の TSMC 社で EUV を使った 5 nm以降の プロセスを使って量産される AXX チップが搭載されている。
現在はさらに4nmへと微細化が進んでいる。また、三星電子はEUV 露光装置をメモリの量産ラインに導入し、量産を行っている。EUV 露光装置の出荷台数(見込)は、2019 年に累積 34 台、2024 年には 250 台を超えると予想される。まさに EUV リソグラフィ量産時代に突入したと言っても過言ではない。
本講演では、まず最近の世界のEUVリソグラフィ向け光源(露光用、検査用)の最新開発動向について解説する。さらに日本の優れたEUV材料開発を支援するために、九州大学が2024年7月に設立したEUVフォトン社の現状と今後の活動計画についても紹介する。
レーザー生成プラズマEUV光源と短波長化などの動向
宇都宮大学 東口 武史 氏
極端紫外 (Extreme ultraviolet, EUV) 光によるリソグラフィーが稼働し始めてから、CPU、GPU、DRAMの高性能化が急速に進み、省電力で高速処理ができるスマートフォンやPersonal Computer (PC) が登場した。
最近は生成AI向けのGPU が活況である。半導体デバイスの製造にEUV露光装置が用いられている。EUV露光装置が我が国に設置されることになった。EUV露光装置はオランダのASML社のみが製造できる唯一の最重要装置であり、EUV露光装置に限ってはASML社の独占状態にある。
現在のEUV露光機のEUV光源の出力は1.2 MWの電力で約500 Wである。フィードバックを行わない制御方式(オープンループ)で、100 kHzの繰り返しにする試行で740 Wの出力が達成されている。この高出力化を図るため、繰り返し周波数を50 kHzから100 kHzにあげ、Sn液滴ターゲットの間隔を拡げる必要があり、液滴ターゲットを押し出すタンクの背圧を700気圧にしている。一方、消費電力は非常に大きい(1 MW級)ため、省エネ化(グリーン化)やエネルギー効率を高効率化する必要がある。
EUV光源の高出力化とともに消費電力も増大するものの消費電力を削減する方策は見いだされていないのが現状である。EUV光源の省電力化にはレーザーからEUV光へのエネルギー変換効率を高めることなどが必要である。
ここでは、CO2レーザー生成プラズマEUV光源の高効率化の数値解析(シミュレーション)を通して高効率化への条件や、低出力レーザーを複数組み合わせるマルチビーム照射法などの方法の有効性など、短波長化への可能性も含め、最近の動向を示す予定である。
●入門程度(大学一般教養程度)
フォトマスク検査機へのEUV光源適用技術
レーザーテック(株) 宮井 博基 氏
半導体デバイスの高機能化、動作速度向上、消費電力低減のため、EUV露光を用いた電子回路パターンの微細化が進められています。
EUV露光で用いられるフォトマスクの検査ではウェハに転写する欠陥を確実に検出する特性が求められるため、露光と同じ波長であるEUV光を用いた検査が必要とされています。EUV光は従来から広く用いられてきた紫外光や可視光とは異なり、大気中で減衰するために光路を真空に引く必要があることや、反射型ミラーを用いて光学系を構成する特殊技術が必要になります。
本講演では検査機に求められるEUV光源および光学系の特性を解説すると共に、検査機向けEUV光源のマスクパターン検査機への適用事例を紹介します。
●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
併催イベント一覧へ
2025年04月25日(金)
13:40-16:35
アネックスホール F204
【UV-3 】
紫外線のアプリケーション
半導体分野におけるUVレーザー穴あけ加工
三菱電機(株) 平山 望 氏
2000年前後、半導体の微細化に対応する高密度実装基板の工法としてビルドアップ工法が進展した。ビルドアップ基板では異なる回路層間を電気的に接続するためのビア穴が必要であり、ビア穴を形成する手段として、CO2レーザーを光源とするビア用レーザー穴あけ加工機が開発された。
近年ではIoT市場拡大、生成AI普及、自動車(CASE)等による多用途・多品種要求に対応するため、半導体チップの微細化の進展とともに半導体パッケージ基板のパターンの高密度化が進み、ビア穴に関しても小径化が要求されている。UVレーザーは従来のCO2レーザーに対して波長が1/30程度と短く、また様々な材料に対して吸収率が高いため微細加工に適した光源であり、当社でもUVレーザーを光源としたレーザー穴あけ加工機の開発を行っている。
本講演では、ビア用レーザー穴あけ加工に関して紹介し、UVレーザーを用いた加工の利点および特に半導体基板に使用される材料に対するUVレーザー加工結果等に関しての紹介を行う。
●入門程度(大学一般教養程度)
光造形技術の最新動向 ― 多様な造形技術・材料開発からマルチマテリアル造形まで ―
横浜国立大学 丸尾 昭二 氏
3Dプリント技術(付加製造技術)は新しいものづくり技術として高い注目を集めています。
なかでも、光造形法は、最も高精度かつ高分解能な3Dプリント技術であり、高出力UVレーザーを用いた大型3Dモデルの造形からフェムト秒パルスレーザーを用いたマイクロサイズの3D微小構造体の作製まで幅広いスケールで活用されています。最近は、適用材料のバリエーションも急増しており、従来の光硬化性樹脂に加えて、セラミックスや金属、導電性高分子、ゲルなど幅広い材料が利用できるようになっています。
また、より高機能な3D部品を製造できる複数材料を用いたマルチマテリアル3D造形技術の研究開発・実用化も活発に行われています。このため、光造形法は、工業製品や精密部品だけでなく、フォトニクス、マイクロマシン、再生医療、歯科などさまざまな分野に応用が拡大しています。
本講演では、紫外レーザーに加えて、青色レーザー、フェムト秒レーザーなどさまざまなレーザー光源を用いた光造形技術に関する最新情報を提供し、多様な光造形用材料の開発動向と応用事例についても紹介します。
●入門程度(大学一般教養程度)/●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
有人下で使用するFar UV-Cの安全性と効果、今後の展開について
ウシオ電機(株) 大橋 広行 氏
これまで紫外線はヒトがいる環境ではなく、密閉された空間に限定して主に波長254nmのUV-C光源が広く使用されてきました。
UV-C光源は細菌やウイルスに対して高い不活化効果を示しますが、ヒトに対して急性障害(紅斑、角膜炎)、慢性障害(皮膚ガン等)を引き起こす可能性があるため、ヒトがいる環境での使用は避けられてきました。
一方、波長222nmの紫外線は波長254nmの紫外線と同様に、細菌やウイルスに対して高い不活化効果を持ちながら、254nmと比較し生体への安全性が極めて高いことが複数の研究機関などで明らかとなっております。
この波長222nmを含む200-230nmの波長域をFar UV-C(遠紫外線)として活用するために開発された紫外線除菌技術Care222の安全性について、従来のUV-C光源(254nm)と比較して詳しく紹介するとともに、新型コロナウイルスSARS-CoV-2などへの不活化効果についてもご説明します。
また、光源および照射機の性能をご紹介するとともに、これらを使用して行った不活化実験や最新の導入事例、実際ご利用いただいている施設での効果試験などについても報告するとともに、紫外線に関する許容暴露量(TLV)が改訂されたことによる今後の展望、疾病の治療や予防を目的とした医療機器開発などの新たな展開の可能性についてもご紹介致します。
●入門程度(大学一般教養程度)
併催イベント一覧へ
元のページに戻り選択を続ける
よくあるご質問
|
お支払方法
|
●クレジットカード(領収書発行)
|

※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|
 ※有料セミナー キャンセル規程:
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/31までは受講料の50%、4/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては
【こちら】をご確認ください。
購読者割引は
読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。
なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。
【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの
|
[ 特定商取引法に基づく表記 ]

平山 秀樹
(国研)理化学研究所
主任研究員
1994年 東京工業大学電子物理工学専攻博士課程修了(工学博士)
1994年 理化学研究所入所
2005年 テラヘルツ量子素子研究チーム、チームリーダー(現職)
2012年 平山量子光素子研究室、主任研究員(現職)
(兼務)埼玉大学連携教授、東京理科大学客員教授、徳島大学招聘教授
(公職歴) 応答物理学会理事(’21-22)、JJAP/APEX誌編集長(‘22)、NPO法人日本フォトニクス協議会理事・紫外線研究会委員長、NPO法人皮膚光線治療促進の会理事
清原 和裕
(株)坪田ラボ
研究開発本部 脳中枢領域開発部 部長
2009年 九州大学大学院薬学府創薬科学専攻修士課程修了。2023年、同大学にて博士号取得。
2009年、田辺三菱製薬株式会社(現・創薬本部ニューロサイエンスユニット)に入社以降、神経科学領域の薬理研究、プロジェクトマネジメント、管理職に従事し、主幹研究員・マネジャーなど歴任。非臨床チームのリーダーとして創薬研究の早期から臨床フェーズへの移行、開発品目や上市品目の価値最大化などの幅広いフェーズのプロジェクトを経験。
2025年2月より株式会社坪田ラボにて脳中枢領域の研究開発を担当。
博士(創薬科学)、薬剤師。
Society for Neuroscience、日本HTLV-1学会、各会員。
溝口 計
九州大学
プラズマ・ナノ界面工学センター 客員教授
EUVフォトン社
取締役 兼 CTO
1982年九州大学総合理工研究科修了。同年コマツ入社、以来CO2レーザ、エキシマレーザ、EUV光源の研究開発に従事。2000年にギガフォトン(株)創業。同社の研究開発部門の責任者を長年務めた、2008年から2018年まで同社代表取締役副社長(兼)CTOを歴任。2023年3月ギガフォトン社を定年退職。
現在、九州大学プラズマ・ナノ界面工学センター客員教授、EUVフォトン社取締役 兼 CTO,
SPIEフェロー。工学博士(1994年九州大学工学部)。日本レーザー学会 諮問委員、正会員。日本応用物理学会 正会員。IAAM会員。レーザー学会産業賞を授賞(2010年、2020年),一般財団法人 光産業技術振興協会 第33回桜井健二郎氏記念賞受賞(2017年)
東口 武史
宇都宮大学
工学部 教授
宮崎大学助手,宇都宮大学助教,准教授を経て,教授.現在,工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース.
これまで,米国ブルックヘブン国立研究所,英国オックスフォード大学, アイルランド国立大学ダブリン校,チェコ科学アカデミー物理学研究所で客員教授,客員研究員.
EUV光源,高繰り返しレーザー,光計測,医用生体工学などの研究に従事している.
宮井 博基
レーザーテック(株)
技術五部 部長
1999年 横浜国立大学大学院修士課程を卒業
2002年 レーザーテック株式会社に入社以降、半導体検査装置の開発に従事
2009年にEUVマスクブランクス欠陥検査機の開発を開始。2013年 のPhotomask Japanでは同装置の発表でベストプレゼンテーションを受賞。2018年にはEUVマスク検査技術の開発がマスク業界に貢献したことから、SPIEよりBACUS Awardを受賞。
2019年にはEUVマスクパターン検査機の開発に世界で初めて成功し、国際学会SPIE Photomask Technology + EUVLにてベストプレゼンテーションを受賞。
平山 望
三菱電機(株)
先端技術総合研究所
2012年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。同年、三菱電機株式会社に入社。
固体レーザー発振器および波長変換技術の開発、ならびにレーザー加工システムの開発に従事し、現在に至る。
現在、次世代半導体パッケージ加工用の深紫外ピコ秒レーザー加工機の開発に従事。
丸尾 昭二
横浜国立大学
大学院 教授
1997年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。名古屋大学リサーチアソシエイト・助手、日本学術振興会特別研究員を経て、2003年より横浜国立大学大学院工学研究院助教授。2014年4月から同大学院教授。専門は、3次元マイクロ・ナノ光造形技術の開発とその応用。内閣府SIPプロジェクト(2014-2018)では、マルチスケール3D造形システムの開発と産学連携オープンイノベーションを推進。JST CREST(2019-2025)では、マルチマテリアル3Dプリンティングの研究開発を推進。
大橋 広行
ウシオ電機(株)
光プロセス事業部 HLS GBU 第二技術部
バイオフォトニクス エグゼクティブ スペシャリスト
2007年 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 博士課程修了
2007年 University of Cambridge Department of Biochemistry 助教
2013年 ウシオ電機入社
2019年 Care222プロジェクトリーダー
2023年 事業創出本部 フードソリューション部 部長
2024年 光プロセス事業部 HLS GBU 第二技術部
バイオフォトニクス エグゼクティブ スペシャリスト