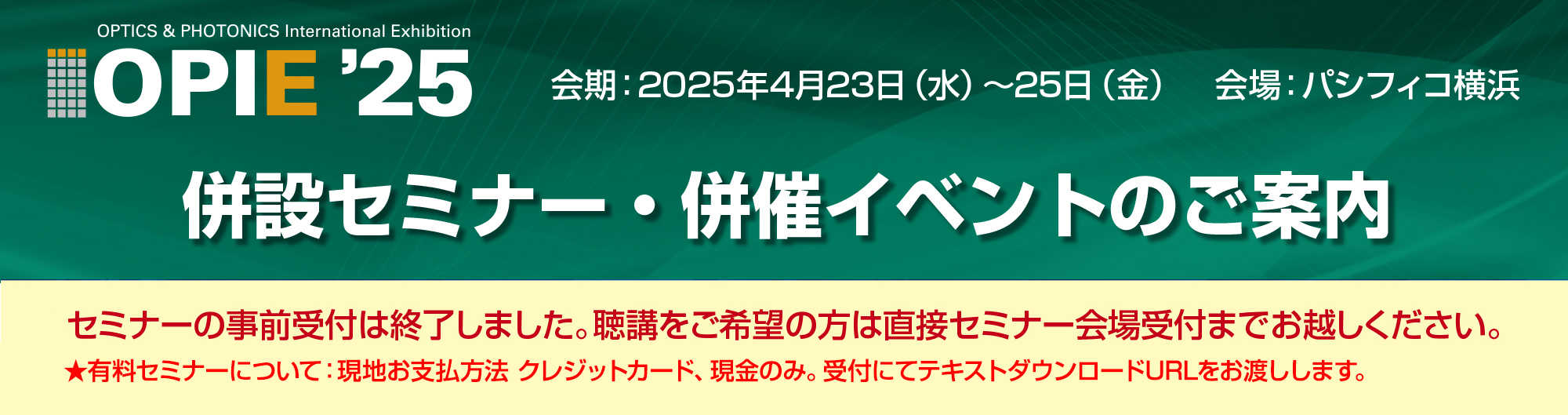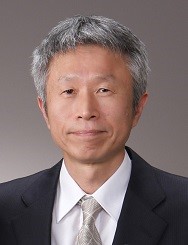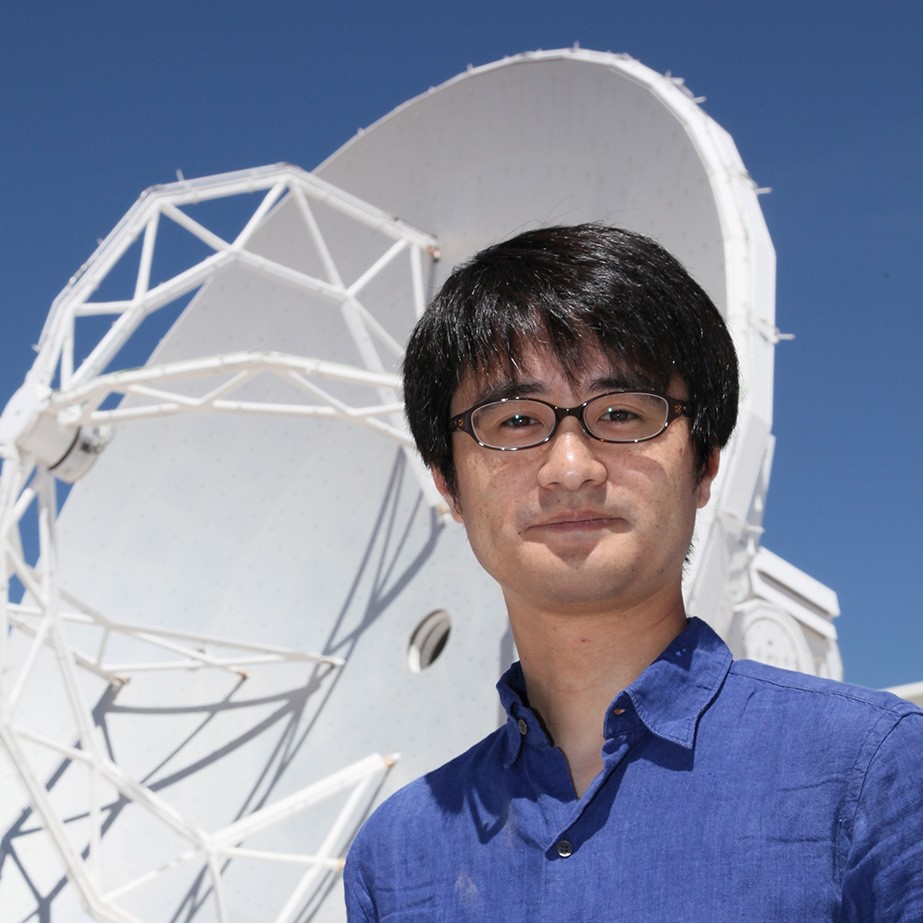宇宙・天文光学 特別技術セミナー
2025年04月24日(木)
09:30-12:25
アネックスホール F203
【SA-1 】
JAXAの研究者が語る宇宙コース
商業デブリ除去実証(CRD2) フェーズⅠと赤外カメラ
宇宙航空研究開発機構 岡田 尚基 氏
CRD2プログラムは非協力ターゲットである宇宙デブリへの接近・除去技術を民間企業が獲得することを目指したJAXAのプログラムです。
このプログラムは2段階の実証となっており、第一段階のフェーズⅠでは、軌道上を周回するH-ⅡAロケット上段をターゲットとして、ターゲットへの接近と画像取得を行うことが目的でした。CRD2フェーズⅠプロジェクトの衛星ADRAS-Jは、2024年2月に打ち上げられ、軌道上のロケット上段の撮影に成功しています。
ターゲットへの接近においては、ターゲットと自身との相対関係を計測する必要があります。ADRAS-Jではこの相対航法のために複数のセンサが搭載されていて、その一つに赤外カメラがありました。
本講演では、CRD2フェーズⅠプロジェクトの概要を紹介するとともに、相対航法センサとして赤外カメラを用いる際に必要となる、模擬画像を用いた地上試験技術について紹介します。
●一般的(高校程度、一般論)/●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
宇宙開発におけるテラヘルツ技術開拓
宇宙航空研究開発機構 西堀 俊幸 氏
国際宇宙ステーション(ISS)搭載の超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(JEM/SMILES)開発から宇宙用複合材を使ったテラヘルツアンテナ開発など、宇宙開発として取り組んだテラヘルツ波の観測機器の開発から学んだ事を中心に、当時のエピソードなども交えて説明する。
●入門程度(大学一般教養程度)
宇宙機の航法センサとしてのLIDAR
宇宙航空研究開発機構 水野 貴秀 氏
近年、月、惑星、小惑星、彗星に対して、多くの探査機が送り込まれ本格的な科学観測や生命探査が行われている。これらの探査機の多くは地形マッピングなどの科学観測や着陸航法用のセンサとしてLIDAR (LIght Detection And Ranging)を搭載している。
「はやぶさ」(2003)、「はやぶさ2」(2014)においてLIDARは、航法用センサとして2度の着陸とサンプル取得に貢献した他、3次元地形測定や重力測定を行って多くの科学成果をもたらした。2026年の打ち上げを目指す火星衛星探査機(MMX)にも100km~100mのレンジを持つLIDARが搭載されている。
一方、2024年1月に世界に先駆けて、月面へのピンポイント着陸に成功したSLIMのように、月や惑星表面へのピンポイント着陸をおこなう探査機では、着陸直前に地形掌握、障害物回避の必要から、高度数百mから3次元イメージが取得可能なセンサが強く望まれている。2023年に小惑星Bennuのサンプルを持ち帰ったOSIRIS-REx(2016)では、科学観測用のスキャン型OLAに加えて、着陸直前の障害物検出のためにFlash LIDARを装備しており、JAXAにおいても障害物センサや軌道上ランデブーのための航法センサとしてFlash LIDAR開発が行われている。
本講演では、火星衛星探査機MMXに搭載されるLIDAR、およびJAXAが開発しているFlash LIDARのための3Dイメージセンサについてご紹介する。
●入門程度(大学一般教養程度)
併催イベント一覧へ
2025年04月25日(金)
09:30-12:25
アネックスホール F203
【SA-2 】
国立天文台を活用する研究者が語る天文コース
見えない宇宙を観る技術を社会へ:国立天文台の技術開発と産業連携
国立天文台 平松 正顕 氏
国立天文台は、天文学研究を推進する日本の代表的な機関の一つです。
日常生活に必要な暦や時刻の決定という伝統的な役割を引き継ぎながら、最先端の技術を駆使して天文観測装置を開発・運用し、様々な宇宙の謎に挑んでいます。
可視光や赤外線、電波を捉える地上望遠鏡、太陽の活動や星の精密な位置を測定するための人工衛星、惑星探査機、重力波望遠鏡、シミュレーション天文学を推進するスーパーコンピュータに至るまで多様な研究環境を整備し、日本と世界の天文学研究を支えています。
国立天文台の活動の特徴は、こうした研究環境整備に必要な技術を自ら開発していることです。
観測装置の設計、製作、システム試験から評価に至るまでの一貫した開発体制を持ち、精密機械加工や積層造形、光学設計や熱設計の技術を高めてきました。
天文学のための技術は光や電波の高感度センシングに直結し、マイクロ波技術は次世代通信(Beyond 5G/6G)や量子コンピュータへの応用が期待されます。天文研究で生み出されるビッグデータを高速で処理するデータベース技術や可視化技術の開発も進めています。
本講演では、国立天文台の活動を技術開発に重点を置きながら紹介し、さらに社会への応用可能性を探る取り組みと産業連携活動についてお話します。
●一般的(高校程度、一般論)
補償光学による光学揺らぎの補正 : 観測天文学から基盤技術の社会実装を目指して
国立天文台 服部 雅之 氏
補償光学系は媒質の揺らぎによる擾乱を光学的に補正する手法です。
補償光学は、画像処理と異なり、入射光の位相分布の揺らぎを補正しますので、ボケ画像の回復以外にも広範な応用が期待されます。
例えば、大気の密度揺らぎによる入射光の位相擾乱を補正することで、天文分野において撮像の分解能向上と共に分光観測の精度の向上が実現しており、あるいは、通信分野において空間光通信の速度を向上する研究がすすんでいます。
また、光学系の拡大・縮小という観点から、天体望遠鏡の対極となる光学顕微鏡においても、観察対象となる生物組織それ自体による揺らぎを補正する研究が進められています。
補償光学はその原理についても興味深く、収差論、光の干渉や回折、そして、波長以下の高精度での光の位相収差の測定と補正など、光学分野の基礎的な事柄を多く含みます。
さらに、補償光学による光学的な補正の有効性を確保するためには、光学収差の元となる大気揺らぎの物理的・時空間的性質や、顕微鏡であれば試料の生物学的性質などの検討が重要となり、そのため、分野融合研究の色彩が強くなります。
本講演では講演者自身の、長年の基礎から応用まで、多岐複数分野に渡る研究開発での実際の経験を踏まえつつ、補償光学の可能性を俯瞰します。
●入門程度(大学一般教養程度)
星と惑星の誕生を見つめて:すばる望遠鏡、JWSTとTMTが拓く新たな宇宙
国立天文台 安井 千香子 氏
星や惑星の誕生過程は、天文学における最も深遠な謎の一つです。この解明に向け、ハワイのすばる望遠鏡、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)、そして開発が進められている30メートル望遠鏡(TMT)といった最先端の望遠鏡が活躍しています。
すばる望遠鏡は1999年のファーストライト以来、その高い解像度と広視野を活かし、星形成領域や原始惑星系円盤の詳細な観測を行ってきました。私たちは、銀河系の外縁部という太陽近傍とは異なる環境下での星や惑星の形成を探る研究を進めています。特に、重元素が少ない領域での星や惑星の誕生を明らかにするため、独自の観測を行っています。
地上の観測と連携し、2021年に打ち上げられた口径6.5mの大型宇宙望遠鏡JWSTは、より高感度の赤外線観測を駆使した画期的な成果を生み出しています。その観測によって、非常に若い原始星、若い星から噴き出す複数のジェット構造、特徴的な星間ダストの分布などを鮮明に捉えることができました。
さらに2030年代には、日本、アメリカ、カナダ、インドが共同で開発を進める口径30mの超大型望遠鏡TMTが本格稼働する予定です。これにより、これまで観測が難しかった微弱な天体やさらに遠方の星形成領域を高精度で捉えることができます。その膨大なデータによって、宇宙の構造や進化の理解がさらに深まることが期待されています。
本講演では、これらの最先端望遠鏡を用いた最新の研究成果を紹介し、星や惑星の誕生に関する新たな知見と、今後の展望についてお話しします。
●入門程度(大学一般教養程度)
併催イベント一覧へ
元のページに戻り選択を続ける
よくあるご質問
|
お支払方法
|
●クレジットカード(領収書発行)
|

※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|
 ※有料セミナー キャンセル規程:
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/31までは受講料の50%、4/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては
【こちら】をご確認ください。
購読者割引は
読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。
なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。
【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの
|
[ 特定商取引法に基づく表記 ]

岡田 尚基
宇宙航空研究開発機構
究開発部門 CRD2フェーズⅡプロジェクトチーム
主任研究開発員
2008年 京都大学情報学研究科修士課程修了、宇宙航空研究開発機構(JAXA)入社
2008~2016年 JAXA宇宙科学研究所にて科学衛星のデータアーカイブシステムを開発
2018年からJAXA研究開発部門にて航法センサ及び画像航法アルゴリズムの研究開発に従事
西堀 俊幸
宇宙航空研究開発機構
研究開発部門 センサ研究グループ
シニアアドバイザー
1963 年滋賀県生まれ.1995年上智大学大学院理工学研究科博士後期課程修了,博士(工学).IHI石川島播磨重工業株式会社,東京都立航空工業高等専門学校講師を経て1998年から現職.筑波大学客員准教授を併任.専門はレーダリモートセンシング,テラヘルツリモートセンシング.日本航空宇宙学会,電子情報通信学会,日本天文学会等会員.
水野 貴秀
宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所 教授
1993年 横浜国立大学大学院工学研究科修了、学位取得。
現在、JAXA宇宙科学研究所教授。
宇宙機搭載用の測距システムを専門としている。小惑星探査機「はやぶさ」、「はやぶさ2」搭載の航法・科学観測用LIDARの開発を担当し、小惑星着陸とサンプル採取の成功に貢献した他、小型月着陸実証機SLIMの着陸レーダの開発を主導し、世界初のピンポイント着陸の成功に貢献した。近年ではG&NC用のFlash LIDARに関する研究開発に取り組んでいる。
平松 正顕
自然科学研究機構 国立天文台
研究力強化戦略室 産業連携室長・講師
2008年、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修了、博士(理学)。台湾中央研究院天文及天文物理研究所博士研究員を経て、2011年から自然科学研究機構国立天文台助教、アルマ望遠鏡東アジア教育広報主任。2021年より、国立天文台天文情報センター周波数資源保護室 講師、2023年より同室長。2019年の国立天文台産業連携準備室立ち上げから参画し、2023年より産業連携室長。良好な電波天文観測環境及び可視光赤外線天文学観測環境の維持のための様々な取り組みを進めるのと並行して、国立天文台の知的資産を社会に活かすための活動を推進している。
服部 雅之
国立天文台
先端技術センター 特任助教
1998-2001 早稲田大学理工学部 応用物理学科助手 (回折格子マスクによる波面計測と液晶光変調器を用いた小型補償光学系・画像回復・ナノ光学等)
2001 通信総合研究所 研究員 (光宇宙通信での波面制御)
2002-2013国立天文台 研究員(講師等) (すばる望遠鏡の補償光学)
2013-2017 基礎生物学研究所 研究員 (分野間連携、補償光学顕微鏡)
2017 電気通信大学 研究員
2017-現在 国立天文台 特任助教 (先端技術センターにて補償光学の基礎と応用の研究、Thirty Meter Telescope撮像分光観測装置IRISに関わる開発)
学位: 博士(理学) 早稲田大学大学院
安井 千香子
国立天文台
TMTプロジェクト 助教
2005年3月 東京大学理学部天文学科 卒業
2010年3月 東京大学大学院理学系研究科博士課程 修了
2010年4月-2012年3月 国立天文台 研究員
2012年4月-2016年4月 東京大学大学院理学系研究科 特任研究員
2016年5月-現在 国立天文台 TMT プロジェクト 助教