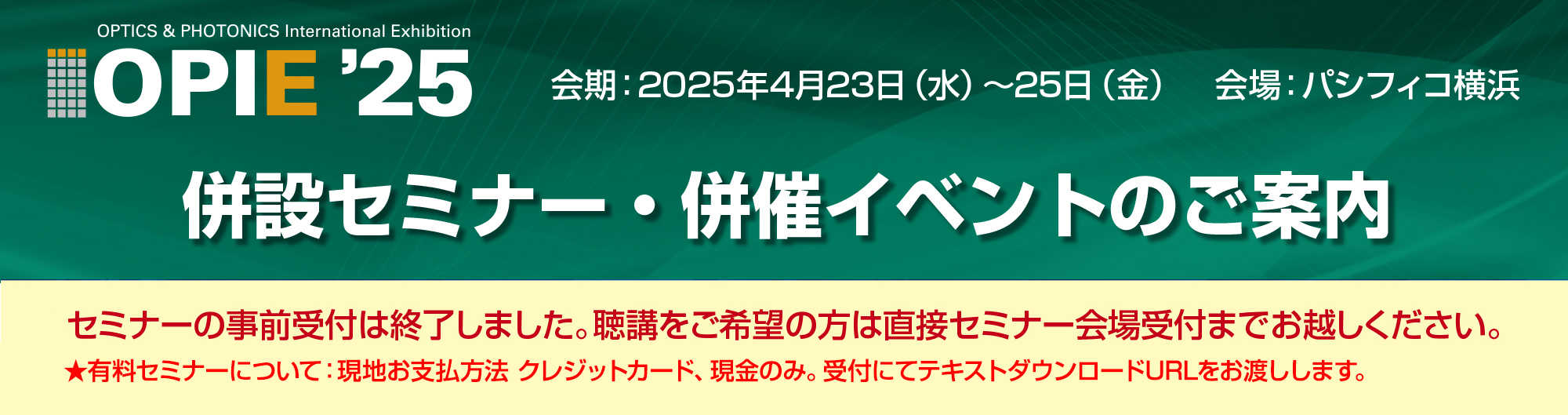NICT(情報通信研究機構)の研究者が語る最新研究
2025年04月25日(金)
13:30-15:50
アネックスホール F203
【NIC-1 】
NICT(情報通信研究機構)の研究者が語る最新研究
NICTにおける衛星地上間光通信の取り組み
(国研)情報通信研究機構 斉藤 嘉彦 氏
衛星-地上間の通信における高速化を目指す上で空間光通信は有望な手段として近年研究・開発が進められています。情報通信研究機構では社会的に注目を浴びるよりも以前から衛星-地上間の光通信の実証実験に取り組んできました。
また、ここ数年では衛星だけではなく様々な飛しょう体を用いた空間光通信の研究開発も注目を浴びています。当機構ではこのような状況のもとで、衛星地上間の光通信技術をさらに一般的な空間光通信に拡張すべく様々な取り組みを行っています。
静止軌道上の衛星と地上間の光通信を実証する計画である、技術試験衛星9号機に搭載された光通信ターミナルを用いた実証や、小型衛星に搭載する小型光ターミナルの実証を行うCubeSOTAのミッション、さらにはより将来を見すえた月地球間光通信用の衛星搭載光学系の研究開発もおこなっています。
また地上系ではそれらの衛星からの通信光を受けるための光地上局の研究開発を行っており、2023年には光地上局をさらに増築し、テストベッドとしての運用も順次開始しています。
さらに空間光通信では避けて通れない大気の影響を克服する研究開発も行っており、特に大気を通過してくる際に劣化したビームの波面を補正する補償光学系の整備も様々なミッションに対して行っています。この講演では、これらの取り組みの紹介をします。
大規模空間・波長多重技術を用いた超大容量光ファイバ通信システムの研究開発
(国研)情報通信研究機構 古川 英昭 氏
将来のSociety5.0社会では、サイバー空間と実空間が融合したサイバーフィジカルシステムを通じて、スマートシティやスマートファクトリ、防災・防犯システムが実現され、様々な社会課題の解決や経済活動の持続的な成長、安全・安心な社会の構築が期待されている。
一方で、通信トラヒックは国内外で年率数10%の割合で増大を続けている。今後、AI(人工知能)、VR/AR(仮想/拡張現実)、IoT(Internet of Things)のための通信需要の更なる拡大が予想され、将来の通信インフラへの影響が懸念されている。このため、国内外において、サイバーフィジカルシステムの情報通信基盤である光ネットワークの大容量化に向けた研究開発が活発化している。
将来に向けて光ファイバ通信システムの伝送容量を拡大するには、信号対雑音比の向上、信号の周波数帯域(=波長帯域)の拡大、空間チャネル数の増加が重要となる。
本講演では、光ネットワークの大容量化に向けて、波長帯域の拡大に向けたマルチバンド波長多重技術、空間チャネル数の増加に向けた空間多重光ファイバ伝送技術について、研究開発の最新動向とNICTの取り組みを紹介する。
宇宙天気予報の最新動向
(国研)情報通信研究機構 久保 勇樹 氏
大規模太陽フレアが発生!その後の地球、そして地球上の社会インフラへの影響はどうなる?これらの問いに答えるのが、宇宙天気予報です。
太陽活動が極大期を迎えた今、太陽フレアをはじめとする、様々な太陽活動による社会インフラへの影響が注目されています。太陽活動の社会インフラへの影響を低減し、現在そして未来の人類の豊かな社会生活を実現する、そのために宇宙天気予報は進化を続けています。
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、法律で定められた法定業務として宇宙天気予報を実施している国内唯一の公的機関であり、その前身である郵政省電波研究所が発足した1950年代初めごろには既に、短波通信障害を事前に察知して利用者に伝える電波警報業務を行っていました。この業務は、1988年に宇宙天気予報と名前を変え、現在は24時間365日途切れることなく運用されています。
NICTでは、24時間365日常時太陽活動や地球周辺の宇宙環境の状態を監視し、また、太陽や太陽風、磁気圏、電離圏の観測やシミュレーションを行い、国内外他機関の観測データ等も収集・分析し、宇宙天気に関する様々な情報を配信しています。
本講演では、過去に実際に起こった宇宙天気災害の例を紹介すると共に、NICTで研究されている最新の宇宙天気予報技術の動向、そして宇宙天気予報業務の実際についてお話しいたします。
宇宙から配る暗号鍵で安全な情報共有を地球規模で~衛星-地上間QKDの技術開発~
(国研)情報通信研究機構 小澤 俊介 氏
量子コンピュータの実用化が遠くない未来に実現しようとしていることで、これまで計算量的安全性に支えられていたRSAなどの暗号方式が危殆化しようとしている。量子鍵配送(Quantum Key Distribution,QKD)は、量子力学という物理的な原理を用いた情報理論的安全性に基づいた、これまでとは全く違った暗号鍵の共有方法である。
我々の研究グループは、光ファイバーを用いたQKDネットワークの社会実装試験運用を10年以上継続しているが、このネットワークを離島や大陸間のように地球規模に拡張すべく、衛星を用いたQKDの手法の実証に取り組んでいる。
昨年までに、総務省委託研究による衛星量子暗号プロジェクトにおいて、国際宇宙ステーションに搭載した暗号装置「SeCRETS」を用いて、衛星-地上間QKDの実現に必要な基礎的な技術の獲得と、課題の抽出を完了した。これをふまえ、昨年実施されたJAXAによる宇宙戦略基金の「衛星量子暗号通信技術の開発・実証」に応募し、昨年12月に採択が決定し、現在まさに衛星QKDの実証のための研究・開発が始まろうとしている。
本講演では、量子コンピュータ時代の情報共有の安全性について議論し、現在我々が取り組んでいる衛星QKDの重要性について、エッセンスの解説を交えて紹介する。
併催イベント一覧へ
元のページに戻り選択を続ける
よくあるご質問
|
お支払方法
|
●クレジットカード(領収書発行)
|

※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|
 ※有料セミナー キャンセル規程:
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/31までは受講料の50%、4/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては
【こちら】をご確認ください。
購読者割引は
読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。
なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。
【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの
|
[ 特定商取引法に基づく表記 ]

斉藤 嘉彦
(国研)情報通信研究機構
ネットワーク研究所ワイヤレスネットワーク研究センター
宇宙通信システム研究室 主任研究員
2002年東京大学大学院博士課程修了、博士(理学)。国立天文台光赤外研究部研究員、国立天文台ハワイ観測所RCUH研究員、東京工業大学特任助教を経て、2017年国立研究開発法人情報通信研究機構に入所。
専門は天文学。すばる望遠鏡にて取得した銀河系外球状星団の観測データをまとめて博士号を取得。国立天文台ハワイ観測所では2002年よりレーザーガイド星補償光学系の開発に従事。東京工業大学では遠隔制御望遠鏡の運用・システム改良に携わる。
現在は衛星地上間光通信の中でも主に地上局の光学系関連の研究開発に従事。2021年より現職。
古川 英昭
(国研)情報通信研究機構
ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター
フォトニックネットワーク研究室 室長
2005年大阪大学大学院工学研究科物質・生命工学専攻博士後期課程了.同年,独立行政法人情報通信研究機構に入所.以来,フォトニックネットワーク,光情報処理技術、ネットワークアーキテクチャに関わる研究に従事.2013-2014年総務省情報通信国際戦略局技術政策課研究推進室課長補佐.2013年文部科学省文部科学大臣表彰・若手科学者賞受賞.2015年公益財団法人新技術開発財団市村学術賞功績賞受賞.IEEE,IEEE ComSoc,電子情報通信学会、応用物理学会各会員.博士(工学).
久保 勇樹
(国研)情報通信研究機構
電磁波研究所電磁波伝搬研究センター
宇宙環境研究室 副室長
東京都出身。東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修士課程修了。博士(学術)。1998年4月、郵政省通信総合研究所(現、国立研究開発法人情報通信研究機構)入所。2000年7月より宇宙天気予報技術の研究開発に従事。主に、太陽電波観測、宇宙放射線などの太陽活動に関わる宇宙天気予報技術の研究開発を行うとともに、宇宙天気予報の精度評価法の研究も行っている。また、情報通信研究機構における宇宙天気予報業務の運用責任者として、日々の宇宙天気予報業務を実施するとともに、宇宙天気予報業務に関する国際会議などへも参加している。
小澤 俊介
(国研)情報通信研究機構
未来ICT研究所 小金井フロンティア研究センター 主任研究員
2004年 博士号取得(工学)
2004年‐2008年 東京大学宇宙線研究所研究員
Telescope Array実験プロジェクトに従事
2008年‐2019年 早稲田大学理工学術院研究院講師
先進理工学研究科鳥居研究室にて「CALET」プロジェクトに従事
2019年‐現在 情報通信研究機構研究員
量子ICT研究室所属,衛星量子暗号の研究に携わる