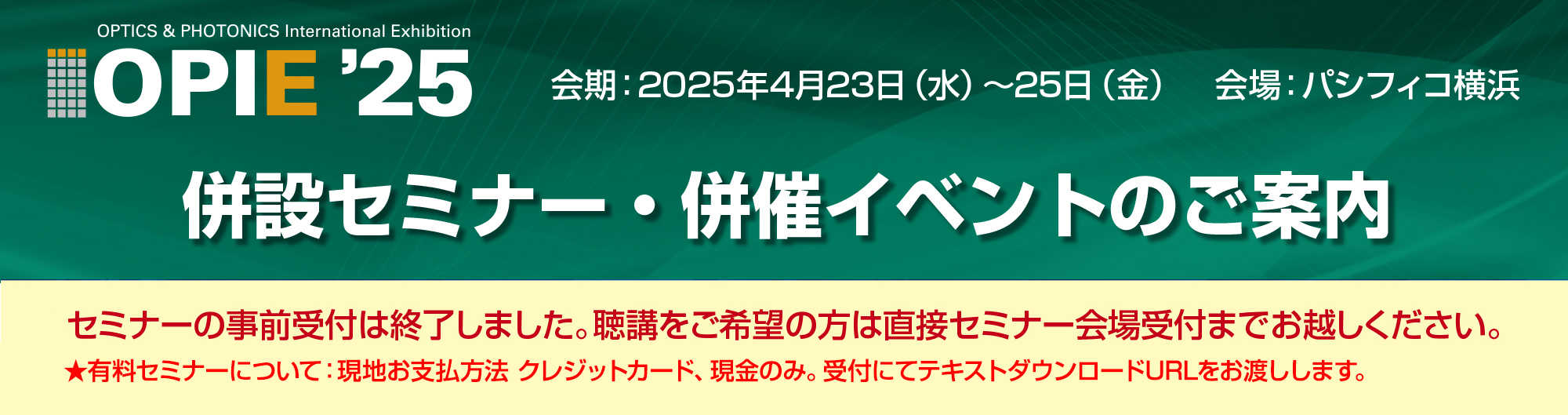応用物理学会フォトニクス分科会主催セミナー
応用物理学会フォトニクス分科会
挨拶
量子インターネット実現に向けた光と物質量子系の研究開発
量子インターネットは、量子通信により量子ビットで世界中を結び付ける。その構築により分散量子コンピュータや量子暗号等の基盤になる期待がされている。
本講演では、量子インターネット実現に向けた研究開発、特に量子中継を構成するハードウェア(量子メモリや量子光源)やそれらの統合技術開発に関して紹介する。また、あわせて当時国内ではおそらく例が無かった量子ハードウェアスタートアップを立ち上げた経緯や、社会実装を目指した取り組みについてもお話する。
光量子コンピュータ超入門 ~基礎から事業化まで~
大規模超伝導量子計算機に向けた超伝導・磁性ハイブリッド量子技術
コヒーレントイジングマシン
|
本セミナーに関する お問い合わせ seminar@optronics.co.jp 件名に【OPIE25】と 記載下さい |
| お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) |
 ※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|

※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/31までは受講料の50%、4/1以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

堀切 智之
LQUOM(株)
最高科学責任者
横浜国立大学
教授
2006年~2007年 日本学術振興会特別研究員
2007年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。
2007年 米国スタンフォード大学ギンツトン研究所visiting scholar。
2008年 国立情報学研究所特任研究員。
2014年 横浜国立大学大学院工学研究院 准教授。
2017年 科学技術振興機構 さきがけ研究員(兼任)
2020年 LQUOM株式会社創業。
2024年 横浜国立大学大学院工学研究院/総合学術高等研究院 教授。
高瀬 寛
OptoQC(株)
代表取締役CEO
1994年兵庫県生まれ。自然豊かな環境で育ち、科学に興味を持つ。2013年東京大学入学、英語演劇に没頭。2016年古澤研究室に配属され、優秀卒業論文賞を受賞。2017年より同研究室で光量子コンピュータの研究に本格的に取り組み、2019年修士号取得(田中昭二賞受賞)、2022年博士号(工学)取得。同年助教に着任後、2024年にOptQC株式会社を設立し、代表取締役CEOに就任。
山下 太郎
東北大学
大学院工学研究科 教授
2005 東北大学大学院理学研究科博士課程後期修了, 博士(理学)
2004 日本学術振興会特別研究員
2006 株式会社ケンウッド
2009 国立研究開発法人 情報通信研究機構 研究員/主任研究員
2016 科学技術振興機構(JST)さきがけ研究者(兼任)
2018 名古屋大学大学院工学研究科 准教授
2022 東北大学大学院工学研究科 教授、現在に至る
専門:超伝導エレクトロニクス、超伝導スピントロニクス
武居 弘樹
日本電信電話(株)
物性科学基礎研究所 上席特別研究員
1996年3月に大阪大学大学院で修士課程修了後、同年4月日本電信電話株式会社入社。同年8月から2003年7月までNTTアクセス網研究所において、光周波数計測、光アクセス網の研究に従事。2003年からNTT物性科学基礎研究所に異動し、以来量子光学、量子通信、光計算の研究を行っている。2004年~2005年スタンフォード大学客員研究員、2014年米国NIST客員研究員。博士(工学)(2002年、大阪大学)。