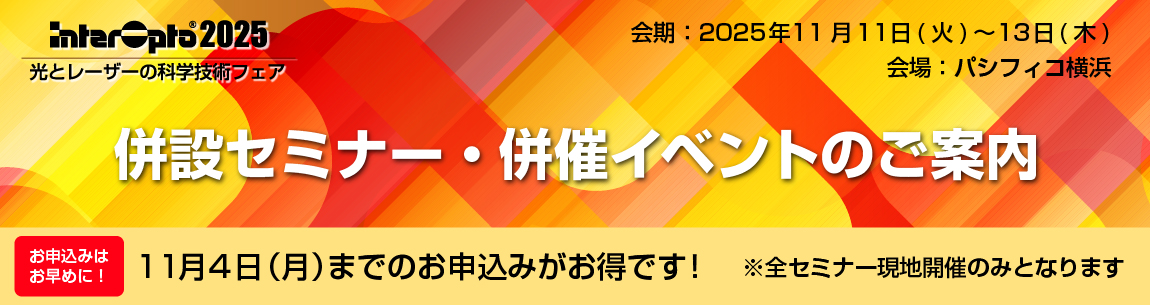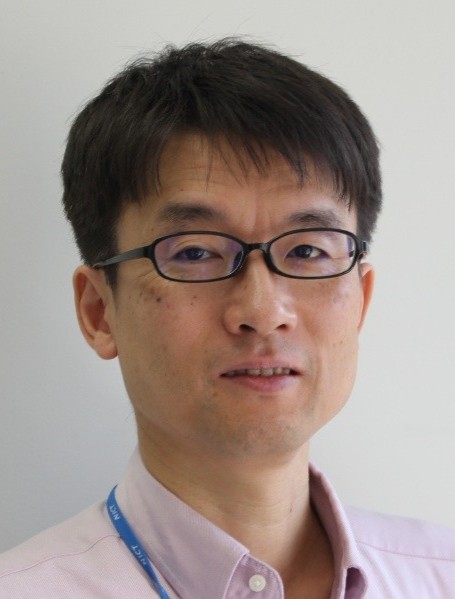光格子時計講演会
2025年11月13日(木)
10:30-12:00
アネックスホール F206
【OLC-1 】
特別講演会『秒の向こうへ、光格子時計の新時代』
光格子時計:これまでの発展の歴史と現在の日本標準時における活用
(国研)情報通信研究機構 電磁波標準研究センター時空標準研究室 室長
井戸 哲也 氏
井戸 哲也 氏
光格子時計は、2001年に東京大学の香取秀俊准教授(当時)によって提案されて以来、飛躍的な発展を遂げてきました。原子を光の定在波格子に捕獲し、多数の原子を同時に観測することで、従来のセシウム原子時計を1桁以上凌駕する周波数安定度と精度を実現する点が大きな特徴です。この性能は、2030年に予定される秒の定義改定に向けて、光格子時計が有力候補とされる根拠となっています。
現在、国際度量衡委員会時間周波数諮問委員会では「単一の原子遷移に基づく定義」と「複数の遷移の加重平均に基づく定義」という2つの方式が議論されていますが、いずれの方式においても光格子時計は最有力候補の一つとして位置付けられています。
本講演では、まず光格子時計の誕生から今日までの発展の歴史を振り返り、その原理と技術的特徴を解説します。
その後、光格子時計が既に日本標準時(JST)に導入され、従来の水素メーザーと組み合わせて時刻系の安定性を高めている、世界でも先駆的な実例を紹介します。実際、日本に在住する皆さんは、放送・通信・インターネットなどを通じて配信される日本標準時を介して、既に光格子時計の高精度の恩恵を日常生活の中で享受しているとも言うことが出来ます。
さらに、将来の可能性として、相対論効果に基づく高精度測位、社会インフラのGNSS過依存を脱却するための時刻アンカーとしての活用、等幅広い展開について議論します。
●初級程度(大学専門程度、基礎知識を有す)
小型可搬ストロンチウム光格子時計の開発
(株)島津製作所 基盤技術研究所 先端分析ユニット
ユニット長 東條 公資 氏
ユニット長 東條 公資 氏
島津製作所はJST未来社会創造事業「クラウド光格子時計による時空間情報基盤の構築」において、東京大学の香取秀俊教授らのグループと共同でストロンチウム光格子時計の開発を行っている。
この時計は18桁の精度を持ち、100億年に1秒の誤差を実現している。現在の標準であるセシウム原子時計に対して100倍以上の高精度であることから次世代の「秒」の定義の候補とされているほか、一般相対性理論を利用した重力ポテンシャル測定(相対論的センシング)による地殻変動や火山活動の監視、標高差計測など多様な応用が期待されている。
島津製作所では、光格子時計を構成するレーザーの堅牢性の向上、レーザー周波数の自動調整・制御技術の開発を実現した結果、世界初の製品化への道筋を付けた。小型化して可搬性を確保したことで、様々なフィールドでの相対論的センシングをはじめ様々な応用が期待できる。
●入門程度(大学一般教養程度)
お申込み受付は終了いたしました。
お支払方法 |
|
●クレジットカード(領収書発行) |
 ※クレジットカード決済後、件名「【ZEUS】決済完了メール(自動送信)」が届いた時点でお申し込み受付完了となります。
|

※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、10/10までは受講料の50%、10/11以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
但し、申込者が既定の人数に達しない場合、中止とすることがあります。その場合には、申し受けた受講料は返金致します。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
※月刊OPTRONICS定期購読者割引:
月刊OPTRONICS定期購読につきましては【こちら】をご確認ください。
購読者割引は読者番号(送本時の宛名ラベルに記載)とお申込み者のお名前が一致している方が対象となります。
|
受講申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。申し込み後、受講者のご都合で欠席となる場合でも受講料は申し受けます。テキスト(pdf)は事前に参加者全員にメールにてお送りいたします。 なんらかの不可抗力により該当セミナー、及び付帯するイベントの開催が不可能となった場合、主催者は受講のキャンセルの受け付け致しません。また、受講料の返金を含む、これにともなった損害の補填・補償は行いません。 【不可抗力】台風、洪水、地震を含む天災、あるいはそれらを原因とする様々な事態、疾病や伝染病の蔓延、労働争議、主催者の合理的なコントロールを超えた会場設備の使用制限や講師の欠席等を含むもの |

井戸 哲也
(国研)情報通信研究機構
電磁波標準研究センター時空標準研究室 室長
東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程を修了後、JST-ERATO研究員、米国NIST/コロラド大学JILAのResearch Associateを経て、2006年にNICTに着任。黎明期から光格子時計の研究に携わり、着任後は光格子時計および精密光計測技術の研究開発を推進するとともに、それらを標準時システムへ導入する取り組みを主導してきた。国際度量衡委員会時間周波数諮問委員会(CCTF)の秒の再定義タスクフォースにおいては、再定義条件充足判定委員会の共同議長を務めている。さらに近年は、時刻・周波数標準技術をモバイル通信分野へ応用する活動にも注力し、XGMFなどを通じて時空間同期技術の普及と発展に貢献している。博士(工学)。
東條 公資
(株)島津製作所
基盤技術研究所 先端分析ユニット ユニット長
1991年大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程修了、㈱島津製作所中央研究所オプトエレクトロニクス研究室に配属。デバイス部レーザ計測グループ長を経て、2020年基盤技術研究所先端分析ユニット副ユニット長、2025年同ユニット長に就任。