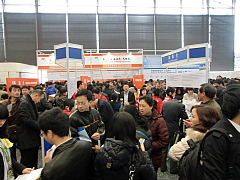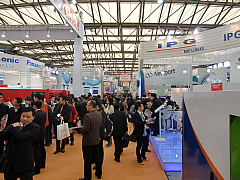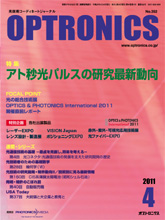
※文中の青い文字にはリンクが貼ってありますので、クリックしてご覧下さい。
東日本大震災で亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。我々は関東大震災や阪神・淡路大震災、また全土が焦土と化した先の敗戦すら乗り越えてきました。今回の未曾有の悲劇をも必ず乗り越えられると信じています。
海外からの声をmsn産経ニュースより幾つか転載させていただきます。中国版のツイッターには、足止めされた通勤客が他の人の通行の妨げにならないよう階段の両脇に座って中央に通路を確保している写真が「(こうしたマナーの良さは)教育の結果。GDPの規模だけで得られるものではない」との説明付きで投稿され、これに対し「我々も学ぶべきだ」といった7万件以上の「つぶやき」があったそうです。環球時報は「日本人の冷静さに世界が感心」と一面見出しで報じました。
ロシア紙ノーバヤ・ガゼータ(電子版)も、社会的秩序を失わずに助け合う日本人の姿を「日本には最も困難な試練に立ち向かうことを可能にする『人間の連帯』が今も存在している」と称え「第2次大戦直後の困難にも匹敵する」大災害でありながら「重要なのは、他の国ならこうした状況下で簡単に起こり得る混乱や暴力、略奪などの報道がいまだに一件もないことだ」と伝えました。
ベトナムのメディアは「怒鳴り合いもけんかもない」「我々が学ぶべき多くのことが分かった」と伝え、バスや公衆電話を我慢強く待つ光景を挙げ「皆が冷静に秩序だって行動していた。こうした強さゆえに、日本人は世界で最も厳しい条件の国土で生き抜き、米国に並ぶ経済レベルを達成できたのだ」と報じています。
インドの日本大使館前では国会議員や有識者、高僧が追悼集会を開き「日本は今回の大災害にも立ち向かう不屈の精神、回復力を持っている」と激励。インド紙ビジネスラインは日本出張中に被災したインド人技術者の「天井や壁が完全に崩れ落ちるような災害の中でも、すべての規律が保たれていた」との報告を載せ、その対応を称賛しました。
米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)もコラムの中で、阪神大震災の際、商店の襲撃や救援物資の奪い合いが見られず、市民が勇気と団結、共通の目的の下に、苦境に耐えていた事に感嘆したとし「日本の人々には真に高貴な忍耐力と克己心がある」「これからの日々、日本に注目すべきだ。間違いなく学ぶべきものがある」と伝えました。
英紙インディペンデント・オン・サンデーは1面トップで日の丸の赤い円の中に「がんばれ、日本。がんばれ、東北。」と日本語の大見出しを掲げ「死者は少なくとも1700人、経済は大打撃、原発では爆発。だが日本は津波の被害から立ち上がろうと闘っている」と報じています。世界が我々の行動を見ています。
今月号の特集は、光科学の最先端ともいえる「アト秒光パルスの研究最新動向」。企画していただいたのは東京理科大学の渡部俊太郎教授です。ご執筆者の皆様もお忙しい中を有り難うございました。
光技術の総合イベント「OPTICS & PHOTONICS International 2011」が4月20日(水)から22日(金)までの3日間、パシフィコ横浜で開催されます。「レーザーEXPO」を始めとした六つの展示会と特別セミナー、関連シンポジウム等を同時開催する一大イベントです。大震災に見舞われた我が国を光産業・技術で再興する! 皆様方の積極的な参加をお願い申し上げます(詳細は今月号関連ページや弊社ウェブサイトでご覧下さい)。