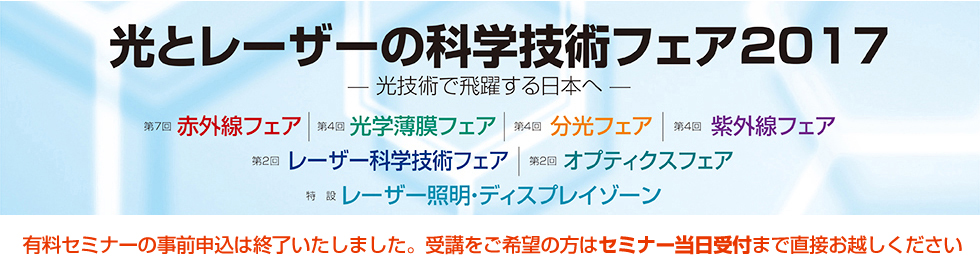-赤外線
赤外線の基礎からハイパースペクトルイメージングまで
1. 赤外線 電磁波の世界 赤外線の分類 赤外線の性質と特徴
2.研究の歴史 赤外線の発見 赤外線からテラヘルツへ
3.伝搬 反射、透過、吸収、散乱と回折および消散 大気の伝搬特性 透過材料
4.熱放射と光源 熱放射に関するキルヒホッフの法則-吸収率と放射率の関係 プランクの法則と黒体放 射 一般の物質の熱放射と放射率 赤外線LED 赤外QCL
5.検出器と感度 赤外線検出器の分類 量子型検出器と感度 熱型検出器と感度
6.雑音と性能指標 量子型および熱型検出器の雑音、NEP、検出能、NETD
7.赤外線計測の方法と応用 ハイパースペクトルイメージングなど
量子型(冷却型)赤外線センサの基礎
量子型赤外線センサの代表的な検知原理は、赤外線の波長によって決まるエネルギに対応したバンド・ギャップ・エネルギ(価電子帯と伝導帯のエネルギ差)を持つ半導体の価電子帯にいる電子が赤外線エネルギを受けて伝導帯に励起し、電流信号として取り出させることを利用するというものです。可視光に比べて小さい赤外線エネルギを如何に高い精度で電気信号に変換するかを中心に、長年に亘り技術開発が続けられています。
また近年、ナノテクノロジによって禁制帯(価電子帯と伝導帯の間のエネルギ準位が存在できない領域)だったエネルギ・レベルに新たな基底準位と励起準位を創生する量子閉じ込め効果を利用した検知デバイスが著しく進展しています。
動作温度と共に増大して信号電流の割合を減らしS/N低下を来す暗電流を大幅に低減する障壁層を設け高動作温度化を可能にするHOT(High Operating Temperature、高動作温度)、システム性能極大化に向けた検知素子ピッチ縮小やアイセーフ・レーザとの整合性が高いSWIR(Short Wave Infra-Red、短波長赤外)域の利用拡大等も注目の的です。
特に、今年、米国での5ヶ年開発プロジェクトVISTA(Vital Infrared Sensor Technology Acceleration、必須赤外線センサ技術加速)の成果発表のトピックスと、赤外線センサ黎明期の主役だったPbSやPbSeが、大幅に低コスト化した量子型センサの開発の候補材料として再浮上している状況もご紹介したいと思います。
赤外線カメラを活用した非破壊検査の基礎
赤外線カメラとその応用
近年、非冷却二次元赤外線センサ(UFPA)が開発され、MEMS技術の向上などにより、狭ピッチ・多画素化、高性能化、低価格化が進み、赤外線カメラの様々な分野で利用が拡大している。その種類は使用目的により、保守保全用ハンディタイプ型、研究開発用高性能多機能型、特殊計測用光学フィルタ内蔵型、計測システム用固定設置型など多岐にわたる。
本稿では、赤外線カメラの動作原理、特徴、性能・機能を有効に活用するための技術、更にその応用例について紹介する。
赤外線観測が切り拓く天文学~天の川銀河の中心とブラックホール
講演では、赤外線による天の川銀河の中心部の観測について紹介する。天の川銀河の中心部は私たちから2万7千光年程度の距離にあり、中心部の円盤状の部分には10億個ほどの恒星が集まっている。これらからの光は、銀河面に存在する星間固体微粒子(0.1マイクロメートルほど)に吸収・散乱され、私たちに届かない。天の川銀河の中心部の恒星を観測できるのは、波長が充分に長くて吸収・散乱を起こしにくい赤外線だけである。
さらにその中心には太陽の400万倍の質量のブラックホールが存在すると考えられている。そのすぐ近くを、楕円軌道を描いて公転している恒星が数十個見つかっており、その中の1つの恒星は来年2018年初めに最もブラックホールに接近する。その運動を詳しく解析することで、極めて強い重力のもとでの一般相対性理論の検証が行なえると考えられている。
また、赤外線の吸収・散乱の波長依存性を調べることで、星間固体微粒子の性質を調べたり、恒星までの距離を精密に求める研究も行なわれている。
新たな中赤外光源:量子カスケードレーザー(QCL)~その開発動向と市場へのアプローチ
本セミナーでは、QCLの構造や動作原理、また発明以降の特性改善や高機能化の歴史を概説した後、センシング分野を中心にQCLの代表的な応用例を紹介する。また、当社におけるQCLの開発事例として、QCLを搭載したセンサーやモジュールの小型化や低コスト化に必須の、QCL低消費電力化に向けた取り組みと、それにより実現した1W動作可能なQCLチップ、及びそれを搭載した、室温CW動作が可能なCANモジュールに関しても紹介させて頂く。最後に、今後のQCLの開発動向や市場動向等に関しても簡単に展望し、本講演のまとめとしたい。


セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、10/15までは受講料の50%、10/16以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。
廣本 宣久
静岡大学
総合科学技術研究科 教授
1978年京都大卒,1985年京都大学理学博士.1984年郵政省電波研究所に入所,1988 年通信総合研究所主任研究官,1995年同光技術研究室長,1999年同企画課長,2001年通信総合研究所関西先端研究センター長,2003年総務省情報通信政策局技術政策課企画官.2005年より静岡大学教授.この間に赤外計測技術,テラヘルツ検出器・センシング技術等の研究において、60 編以上の論文を発表,4件の特許を取得.日本赤外線学会会長,学術振興会第182委員会主査・運営委員,テラヘルツテクノロジーフォーラム理事,応用物理学会,電子情報通信学会,OSA,IEEE各会員.1998年科学技術庁長官賞研究功績者,郵政大臣表彰業務優績個人受賞.
中里 英明
株式会社富士通システム統合研究所
研究理事
1980年03月 東北大学理学部天文および地球物理学科第1卒
1980年04月 富士通株式会社入社。無線事業部・特機技術部に配属。宇宙・防衛用赤外線機器開発に従事
1981年01月 (株)富士通システム統合研究所に出向。防衛用赤外機器研究・開発に特化。以来、防衛用光波システムの研究・開発に従事。
2011年度~ 防衛装備庁電子装備研究所研究試作「遠距離探知センサシステム」に参画。
2012年度~ 「戦闘機の概念設計および3次元デジタル・モックアップ」等将来戦闘機関連事業に参画。
2004年06月~ (一財)防衛技術協会「防衛用赤外・ミリ波技術研究部会」および後継の「赤外・ミリ波センシング研究部会」幹事。
2016年~ 日本赤外線学会執行役員。
森本 広志
株式会社富士通システム統合研究所
先進システム研究所 システム研究部
2007年03月 大阪大学基礎工学研究科卒
2007年04月 富士通株式会社入社。(株)富士通研究所に出向。電子ペーパー開発に従事。
2012年度~ (株)富士通システム統合研究所に出向。防衛用赤外線機器研究・開発に従事。防衛装備庁電子装備研究所研究試作「2波長赤外線センサ」に参画。
2014年度~ 防衛装備庁研究試作「哨戒機搭載システムの対潜能力向上」に参画。
小笠原 永久
防衛大学校
システム工学群 機械工学科 教授
横浜国立大学 生産工学科 卒業
横浜国立大学 工学研究科博士前期課程 中途退学
横浜国立大学 生産工学科 助手
博士(工学)取得 横浜国立大学
防衛大学校 機械工学科 助手
米国コロンビア大学 客員研究員
防衛大学校 教授
赤外線サーモグラフィを用いた非破壊検査および微小押込試験による材料特性評価の研究に従事
笛 憲司
日本アビオニクス株式会社
赤外線サーモグラフィ事業部 技術部 研究開発Gr 兼 マーケティングGr
1999年 NEC三栄株式会社 入社
2000年 赤外機器開発部に配属され赤外線カメラの開発に従事
2017年 現職
長田 哲也
京都大学
大学院理学研究科 宇宙物理学教室 教授
兵庫県立長田高等学校卒業、1980年京都大学理学部卒業、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。ハワイ大学天文学研究所ポスドク、京都大学大学院理学研究科助手、名古屋大学大学院理学研究科助教授を経て、2004年から京都大学大学院理学研究科教授。
専門は赤外線天文学。南アフリカ天文台に日本が設置した小さな赤外線望遠鏡を使って天の川銀河の中心部や、星間物質の観測研究を行なうとともに、岡山に日本初の分割鏡方式による口径3.8m光赤外線望遠鏡を建設している(赤外線も観測できる望遠鏡としては「東洋一」の口径の大きさを誇る)。
橋本 順一
住友電気工業株式会社
伝送デバイス研究所 赤外デバイス研究部 グループ長
1989年住友電気工業株式会社に入社。以後、600nm帯GaInP/AlGaInP系可視光半導体レーザ、EDFA励起用980nm帯GaInAs歪量子井戸半導体レーザ、光通信用1550nm帯ファイバグレーティングレーザ、光通信用GaInNAs系1300nm帯半導体レーザ等の半導体レーザの研究、開発に一貫して従事し、エピ成長や素子設計、特性評価、信頼性評価等の業務を担当した。2007年からは100Gイーサ用EMLや幹線用半導体系マッハツェンダー変調器等、他の半導体光素子開発も手掛け、2010年頃からは新分野として、中赤外領域の開拓にも着手し、主として量子カスケードレーザの開発を統括し、現在に至る。