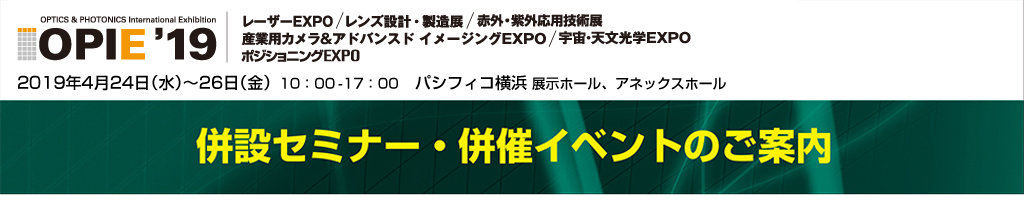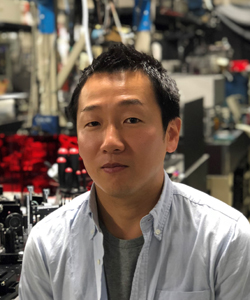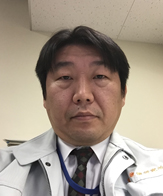・赤外線応用技術セミナー
赤外線の基礎
赤外線など光・電波の波動性と粒子性は分かりにくいと思いますが、媒質中を伝搬する時は主に波の性質、放射・吸収など物質と相互作用する時は粒子の性質があらわれると考えることでほぼ正しい理解になっています。
赤外線は、近年、赤外検出器や光学素子の性能向上、小型化、低価格化によって、その利用が、急速に増大しており、さまざまな応用の可能性が広がっています。技術革新による高度な利用、特性を踏まえた新しい応用を切り拓くために、赤外線の科学的理解の必要性がますます重要になっています。
本講演では、赤外線の科学・技術の基礎をやさしく説明します。
1. 赤外線 電磁波-光、電波と同じもの
2。赤外線の歴史 熱感知、検出器、分光、テラヘルツ
3. 赤外線と物質との相互作用 反射、透過(屈折)、吸収など
4. 赤外線の大気伝搬 大気減衰、大気の窓
5. 熱放射・黒体放射と熱光源 放射率と吸収率、プランクの放射則
6. 赤外光源 熱放射、半導体LED・レーザー
7. 赤外検出器 量子型と熱型、感度と雑音
赤外線光源の動向
本講演では、固体レーザーに非線形周波数変換を利用した中赤外光源や、2µm帯で直接レーザー発振する固体レーザー等の近年の動向について紹介します。
赤外線計測の動向
非冷却赤外線イメージセンサ
本講演では、非冷却赤外線イメージセンサの基礎と最近の技術動向/ビジネス動向を解説する。基礎では、熱型赤外線検出器の動作、熱コンダクタンス低減の意義、受光部の温度をセンシングする手法、分光感度特性を決定する赤外線吸収層の設計などについて議論する。最近の技術動向に関しては、画素ピッチ縮小の動向とこれを可能にしたMEMS技術の進歩、高解像度化と小フォーマットアレイの開発動向、低コスト化への取り組みなどを紹介する。さらに、今後非冷却赤外線カメラ市場を牽引すると考えられている車載ナイトビジョンシステムやスマートフォン用赤外線カメラなどの新市場の動向にも触れる。
赤外線カメラとその応用
近年、非冷却二次元赤外線センサ(UFPA)が開発され、MEMS技術の向上などにより、狭ピッチ・多画素化、高性能化、低価格化が進み、赤外線カメラの様々な分野で利用が拡大している。その種類は使用目的により、保守保全用ハンディタイプ型、研究開発用高性能多機能型、特殊計測用光学フィルタ内蔵型、計測システム用固定設置型など多岐にわたる。
本稿では、赤外線カメラの動作原理、特徴、性能・機能を有効に活用するための技術、更にその応用例について紹介する。
SOIダイオード方式非冷却赤外線イメージセンサ
FTIRに代わる次世代の赤外分析法;量子カスケードレーザを用いた分光分析
CT半導体レーザ吸収法を用いたエンジン筒内の2次元時系列温度分布計測
徳島大学とNTTは地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素ガス排出量削減のために、燃焼や爆発といった現象をリアルタイムに解析する技術の開発を進めている。本講演では前半に二酸化炭素の吸収帯に一致した2μm帯の波長可変レーザを中心としたセンシング用光源について、後半ではそれらの光源とCT(Computer Tomography)-TDLAS法を組み合わせることによって、リアルタイムなエンジン筒内の2次元時系列温度・濃度分布計測への適用について紹介する。
レーザガスセンシングによる安定同位体比分析技術 ~カシミヤ原料の科学的産地推定技術の実証実験について~
本講演では、NTTの保有する分析技術を、高級繊維原料の1つであるカシミヤの科学的原産地推定方法として活用することを目指した検証実験について紹介します。具体的には、安定同位体比分析技術を利用して、カシミヤに含まれる元素の安定同位体比分析を行い、あらかじめ産地情報(地理情報や、飼育情報含む)と関連付けて蓄積された安定同位体比データと照合することによる科学的産地推定手法の有効性検証に関する実験概要について解説します。
カシミヤ原産国では、消費者へ安心して高品質な製品を供給するだけでなく、ブランド化による生産者保護につながるトレーサビリティが確保された管理体制作りが望まれており、その課題解決に向けた応用となることを目指しています。
防衛装備庁における赤外線センサ技術
発表できる範囲は限られておりますが、出来る限り装備品への技術の適用の考え方や将来への方向性が感じられるような内容にしたいと考えております。
中赤外光を用いたヘルスケアモニタリング -非侵襲血糖値測定-
波長が2~12ミクロン程度の中赤外光を用いた分光法により、生体を構成するタンパク質、脂質、糖質などの高精度な分析が可能になるが、これまで分析にはフーリエ赤外分光光度計(FT-IR)などの大型の装置が必要であり、一般的な機器の開発は困難だった。ところが最近、中赤外量子カスケードレーザや、室温動作の半導体検出器が登場し、これらと中赤外光を伝送可能な中空光ファイバを組み合わせることにより小型かつ安価なヘルスケア機器の実現性が高まってきた。
そこで本講演では、はじめに光学的手法による非侵襲血糖値測定法の原理を紹介し、中赤外光を用いることによるメリットについて述べる。次にFT-IRと中空光ファイバを組み合わせたシステムによる血糖値測定を行った結果についての報告を行う。その後、測定システムの小型化、低コスト化を目指し、光源として中赤外域で動作するQCLを新たに導入したシステムについての最新技術を報告するとともに、中赤外光を用いたヘルスケア機器の今後の展望などについて述べる。
農業・食品工学分野への応用

| お支払方法 |
|
●クレジットカード ●当日支払 |

|
セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/25までは受講料の50%、3/26以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

廣本 宣久
静岡大学
総合科学技術研究科 工学専攻 教授
1978年京都大卒,1985年京都大学理学博士.1984年郵政省電波研究所に入所,1988年通信総合研究所主任研究官,1995年同光技術研究室長,1999年同企画課長,2001年通信総合研究所関西先端研究センター長,2003年総務省情報通信政策局技術政策課企画官.2005年より静岡大学教授.この間に赤外計測技術,テラヘルツ検出器およびセンシング技術等の研究において,60 編以上の論文を発表,5件の特許を取得.日本学術振興会テラヘルツ第182委員会委員長,日本赤外線学会前会長,テラヘルツルツテクノロジーフォーラム理事,応用物理学会,電子情報通信学会,OSA,IEEE各会員.1998年科学技術庁長官賞研究功績者,郵政大臣表彰業務優績個人受賞.
湯本 正樹
国立研究開発法人 理化学研究所
光量子工学研究センター 光量子制御技術研究開発チーム 研究員
バトンソーン研究推進プログラム 中赤外レーザー光源研究開発チーム 副チームリーダー(兼務)
2010年 東京理科大学大学院物理学研究科修了
2010~2015年 (独)理化学研究所 光グリーンテクノロジー研究ユニット 特別研究員
2015年~ (国研)理化学研究所 光量子制御技術開発チーム 研究員
2018年~ (国研)理化学研究所 中赤外レーザー光源研究開発チーム 副チームリーダー(兼務)
水谷 耕平
国立研究開発法人 情報通信研究機構
戦略的プログラムオフィス マネージャー
1980年京都大卒,1985年京都大学理学博士.1991年郵政省通信総合研究所科学技術特別研究員,1998年同光計測研究室長.2006年情報通信研究機構センシング・ネットワークグループマネージャー,2011年同センシング基盤研究室総括主任研究員,2018戦略的プログラムオフィスマネージャー.2001-2017年首都大学東京(2004年までは都立科学技術大学)客員教授.専門分野はリモートセンシング、赤外線天体物理学。天文学会、赤外線学会、応用物理学会、米国光学会。
木股 雅章
立命館大学
理工学部 特任教授
1976年 名古屋大学大学院工学研究科修士課程修了。同年 三菱電機株式会社入社。 2004年 三菱電機株式会社退社。同年 立命館大学理工学部教授。1980年より現在まで赤外線イメージセンサの研究開発に従事。2009年よりJAXAのType-II超格子赤外線センサの開発に参画。電気学会、日本赤外線学会、応用物理学会、IEEE会員、SPIEフェロー。2013〜2014年 日本赤外線学会会長。1988年 市村賞貢献賞、1993年 全国発明表彰内閣総理大臣発明賞、2016年 日本赤外線学会業績賞などを受賞。工学博士
宇田 康
日本アビオニクス株式会社
赤外線サーモグラフィ事業部 技術部 研究開発G マネージャー
1999年 武蔵工業大学 工学部 電気電子工学科卒業
1999年 日本アビオニクス株式会社 入社
2002年 赤外線サーモグラフィ装置の開発に従事
2018年 現職
藤澤 大介
三菱電機株式会社
先端技術総合研究所 主席研究員
2002年,豊橋技術科学大学大学院工学研究科電気電子工学専攻 修士課程修了.2005年,同大学院工学研究科電子情報工学専攻 博士後期課程修了.同年,三菱電機株式会社に入社.同年より赤外線固体撮像素子の研究開発に従事し,現在に至る.博士(工学).
秋草 直大
浜松ホトニクス株式会社
レーザ事業推進部 主任部員
1996年 北海道大学工学部 卒業
1996年 浜松ホトニクス株式会社 入社
1997年 同、中央研究所
2009年 同、開発本部
2014年 同、レーザー事業化部
2017年 同、レーザ事業推進部
現在に至る
下小園 真
日本電信電話株式会社
NTT先端集積デバイス研究所 主任研究員
1990年九州大学理学部化学科卒業、1992年九州大学理学部化学研究科修士課程修了。同年日本電信電話株式会社入社し、主に光デバイス関係の研究開発に従事。2010年からは波長可変レーザの研究開発に従事し現在に至る。また2014年からは国際電気標準会議ファイバーオプティクスの専門委員を務めている。
神本 崇博
徳島大学
大学院社会産業理工学研究部 特別研究員
・2016年3月 徳島大学修了(工学博士)
・2016年4月~2017年5月:
徳島大学大学院理工学研究部機械科学コース
学術研究員
・2017年6月:徳島大学大学院理工学研究部機械科学コース
特任研究員
現:社会産業理工学研究部
<兼務 [学外]>
株式会社SL&PS 最高技術責任者
赤毛 勇一
日本電信電話株式会社
デバイスイノベーションセンタライフアシストプロジェクトスマートインフラメンテナンス技術DP
工藤 順一
防衛装備庁
電子装備研究所 センサ研究部 光波センサ研究室長
1995年筑波大学大学院理工学研究科修了。1995年より防衛庁技術研究本部第2研究所(現防衛装備庁電子装備研究所)にて、光波センサシステム、赤外線撮像装置等の研究開発に従事。2015年11月より現職。工学博士。
松浦 祐司
東北大学
大学院医工学研究科 教授
1988年東北大学工学部通信工学科卒,1992年東北大学大学院工学研究科修了,博士(工学).1993年住友電気工業横浜研究所研究員,1994年米国ラトガース大学セラミック工学科研究員として勤務の後,1996年東北大学大学院工学研究科助教授.2008年東北大学大学院医工学研究科教授.X線から遠赤外にわたる電磁波伝送路とその医療応用に関する研究に従事.レーザー学会,電子情報通信学会,応用物理学会,電気学会、SPIE会員.平成17年度文部科学省若手科学者賞受賞.レーザー学会東北・北海道支部長.
吉村 正俊
東京大学
大学院農学生命科学研究科 助教
平成22年 東京農工大学 大学院連合農学研究科 環境資源共生
科学専攻 博士課程 修了
平成22年〜26年 (独)農研機構 食品総合研究所 特別研究員
平成24年〜26年 日本学術振興会特別研究員PD
平成26年〜29年 東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任助教
平成29年〜 現職