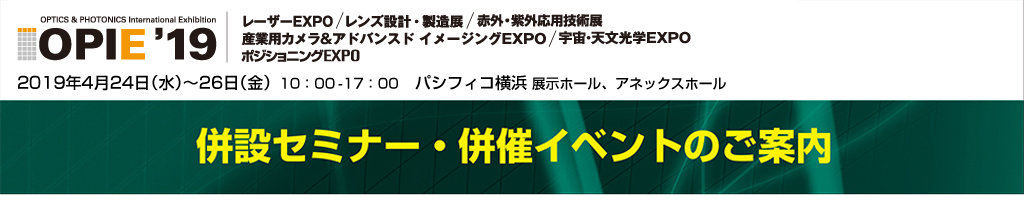・紫外線応用技術セミナー
紫外線の基礎と応用
ε=hν=hc/λ (1) ここで、hはプランク定数、νは振動数、λは波長、cは真空中の光速である。(1)式から、光子のエネルギーは、電磁波の振動数に比例し、波長に反比例することがわかる。原子や分子で構成される物質が光子を吸収して起こす化学反応は、mol単位で行われる。物質1molあたりに含まれる粒子数はアボガドロ定数NA(NA ≒ 6.022 × 1023 mol-1 )と呼ばれる。
1molあたりの光子エネルギーは、光子1個のエネルギーεにアボガドロ定数NAを乗じたものになる。E =NAε=NA hν=NAhc/λ [kJ mol-1] となる。
赤外線や可視光線より波長の短い紫外線の光子エネルギーは大きく、物質に吸収されると電子状態を変化させ光化学反応を起こすことから化学線と呼ばれることもある。
紫外線の光化学反応は、日々の生活を支援している多種・多様な産業に必要不可欠な要素技術を数多く提供している。
本講演では、1.紫外線とは、2.紫外線の放射源 太陽光と人工光源、
3.紫外線の計測法、4.紫外線の人体作用、5.紫外線利用技術と産業応用について述べる。
なお、紫外線の波長帯域区分用語:UV-A、UV-B、UV-Cは、1932年に光療法の普及の過程で提案され、現在は、国際照明委員会(CIE)の定義用語となっている。しかし、研究・産業分野によって同一用語を使いながら、帯域区分波長が異なる場合が多い。
用語UV-A、UV-B、UV-Cを用いて紫外線を論ずるときには波長明記が必須と言える。
殺菌用紫外LEDの開発と今後の展望
固体レーザー、ファイバーレーザーを利用した産業用紫外線レーザー
あるいは、自動車搭載用の電子機器の製造に関しても大きな産業となっている。
本講演では、こういった産業の基盤となる計測、加工の原理を紹介するとともに、
応用に必要な光源技術の基盤の解説をファイバーレーザー、固体レーザー技術を
基盤として開設を行う。
水処理における紫外線殺菌技術の現状と展望
また水道では消毒の要求基準を満たすことが必須であるため、紫外線装置の能力検証が非常に重要視されている。この検証はユニークな方法が実践されているが、その解説と共に、問題点についても紹介する。
また下水処理での紫外線殺菌技術の適用例については、国内外において見ることができる。特に日本における適用拡大の可能性を条例と併せて紹介するとともに、今後の展望として海外で実際に稼働している再生水への適用法を紹介する。その中にはオゾンや過酸化水素といった酸化処理との併用によるAOP(促進酸化処理)も含まれるが、その発展可能性についても紹介する。さらに新光源であるUV-LEDの水処理への適用の可能性などについても今後の展望として紹介する予定である。
光触媒の基礎と応用、未来への展望 ~快適で持続可能な社会のために~
ある種の金属酸化物は、光を当てると、その表面で酸化分解反応などを起こす。しかし、金属酸化物自体は反応の前後で変化しない。金属酸化物が光エネルギーを吸収し、それを使って反応を起こしているのである。これが光触媒反応である。現在、酸化チタンに紫外線を照射することで、この光触媒反応が効率よく起きることが知られており、幅広い分野に応用されている。光触媒関連技術は我が国オリジナルの技術であり、酸化チタンを用いた水の光分解(本多・藤嶋効果)の発見以来、実に50年以上研究開発が続けられている。しかしながら、その知名度や製品の市場が急速に拡大したのは、ごく最近のことである。光触媒技術を応用した製品の事業規模は、ここ十数年で約3倍に増加した。内訳を見ると、浄化機器分野の成長が特に著しい。
本講演では、いくつかのトピックスをとりあげ、実験を交えながら、光触媒の基礎から最新の研究成果、市場の動向および未来への展望などについて述べる。なお、本講演は紫外線の応用例として光触媒を簡単に紹介するものである。すでに光触媒に詳しい向きには、物足りなく感じられるかもしれない。その場合は、適した成書を参照されたい。
紫外線の医療への応用―安全な治療器開発をするために

| お支払方法 |
|
●クレジットカード ●当日支払 |

|
セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/25までは受講料の50%、3/26以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

佐々木 政子
東海大学
名誉教授
東京理科大学理学部化学科卒業.東京大学工学博士.東京大学生産技術研究所文部技官・助手を経て,東海大学に転出.東海大学開発技術研究所・総合科学技術研究所教授を経て,現在,東海大学名誉教授,日本化学会フェロー,日本フォトニクス協議会(JPC)名誉会員など.その間,日本女性科学者の会会長,日本光生物学協会会長,Photochemical & Photobiological Sciences, Associate Editor,JSTさきがけ「光の利用と物質材料・生命機能」領域アドバイザー等を歴任.第1回日本光医学・光生物学会賞,光化学協会功績賞,日本女性科学者の会功労賞,国際照明委員会(CIE)Award等受賞。
平山 秀樹
国立研究開発法人 理化学研究所
平山量子光素子研究室 主任研究員
1994年、東京工業大学大学院電子物理工学専攻博士課程修了、同年、理化学研究所に入所、2005年テラヘルツ量子素子研究チーム、チームリーダー、2012年平山量子光素子研究室、主任研究員。埼玉大学連携教授を兼務。これまで、量子電子・光デバイスの研究、特に窒化物半導体紫外発光デバイスの研究、フォトニック結晶・量子ドットを用いた光デバイス、テラヘルツ量子カスケードレーザの研究に従事。文部科学大臣表彰科学技術賞(2015年)、ドコモモバイルサイエンス賞(2013年)、市村学術賞(2012年)、日本IBM科学賞(2011年)、文部科学大臣表彰若手科学者賞(2005年)、丸文奨励賞(2003年)などを受賞。
和田 智之
国立研究開発法人理化学研究所
光量子工学研究センター 光量子制御技術開発チーム チームリーダー
1992年 東京理科大学大学院博士課程修了 博士(理学)
同年 理化学研究所基礎特別研究員
2012年 理化学研究所 光量子工学研究領域 チームリーダー
2018年 理化学研究所 光量子工学研究センター チームリーダー
高エネルギー研究所、東京理科大学大学院 客員教授
大瀧 雅寛
お茶の水女子大学
基幹研究院 教授
1995年3月 東京大学大学院工学系研究科博士課程を修了した後,
1995年 4月 東京大学大学院工学系研究科の助手として勤務.
1997年11月に同講師として勤務した後,1999年 4月よりお茶の水女子大学大学院人間文化研究科に助教授として就任.以後2012年に同教授,現在に至る.
途中,2000年8月から2001年3月には南フロリダ大学にて客員研究員.
専門は環境衛生工学だが,特に水処理における消毒技術が専門.他にも国内外の都市用水需要の予測に関する研究も行っている.
落合 剛
地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所
川崎技術支援部 材料解析グループ 主任研究員
兼
東京理科大学
研究推進機構 総合研究院 光触媒国際研究センター 客員准教授
平成20年 3月
名古屋工業大学大学院 工学研究科 博士後期課程 物質工学専攻 修了、博士(工学)
17年 4月~20年 3月
JR東海 総合技術本部 技術開発部 機能材料チーム研究員
20年 4月~25年 3月
(財)神奈川科学技術アカデミー 重点研究室 光触媒グループ 常勤研究員
25年 4月~29年 3月
(公財)神奈川科学技術アカデミー 実用化実証事業 光触媒グループ サブリーダー
29年 4月~31年 3月
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 川崎技術支援部 材料解析グループ 主任研究員
兼 同 研究開発部 実用化実証事業 光触媒グループ サブリーダー
31年 4月~現在
(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 川崎技術支援部 材料解析グループ 主任研究員
※その他、東京理科大学 光触媒国際研究センター 客員准教授、(財)北里環境科学センター研究生、日本工業大学・法政大学・東京理科大学大学院の非常勤講師などを併任
※主に、光触媒および導電性ダイヤモンド電極を用いた環境浄化に関する研究に従事。研究成果の実用化をめざし、企業との共同研究や、製品の性能評価を積極的に展開中。平成26年3月、電気化学会進歩賞・佐野賞受賞。
木村 誠
ウシオ電機株式会社
バイオメディカル事業部 MI部門 部門長
昭和61年4月 ウシオ電機株式会社 入社
平成17年3月 桐蔭横浜大学大学院工学部 後期博士課程 卒業
平成17年4月 桐蔭横浜大学 医用工学部 客員研究員
平成24年3月 ウシオ電機株式会社バイオメディカルBU 次長
平成24年4月〜平成26年3月 独立行政法人理化学研究所 分子イメージング科学研究センター 客員研究員
平成26年7月 名古屋市立大学 大学院医学研究科 加齢環境皮膚科学 研究員 平成27年4月 同大学 非常勤講師
医療用光源装置の開発に従事し、高度管理医療機器等販売業責任者、高度管理医療機器等賃貸業責任者、放射線実務従事者を務める。主として、桐蔭横浜大学では細胞を使った光医療の研究、理化学研究所では動物を使った光医療研究を行い、名古屋市立大学では、臨床現場で光治療機器、光診断機器の研究開発に取り組んでいる。光線力学療法、UV療法、スカホールド形成などの装置(Therabeamシリーズ)の研究、開発、販売に取り組んでいる。2003年度材料技術研究会技術賞受賞。日本光線力学学会、日本レーザー医学会、日本光医学・光生物学会会員等。