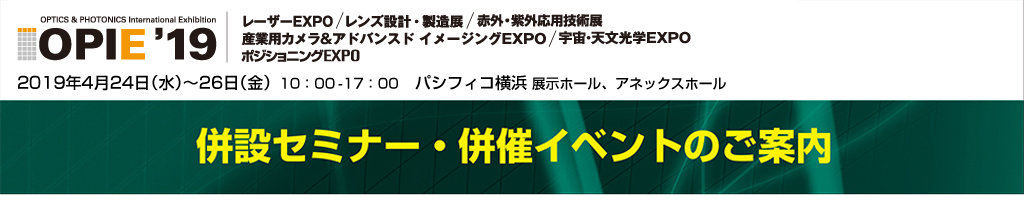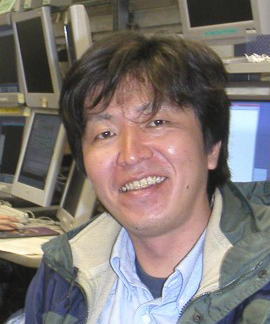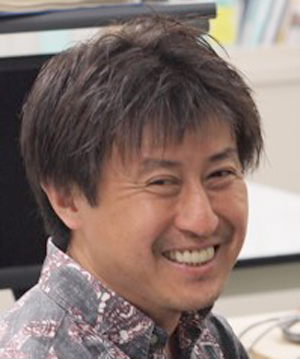・宇宙・天文光学 特別技術セミナー
はやぶさ2が見た小惑星リュウグウ
赤外線で探る宇宙 〜「あかり」の成果を中心に〜
ベピコロンボ計画「みお」が挑む水星探査
超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS)の運用状況
JAXAでは、宇宙空間におけるフロンティア領域の開拓と地球観測利用の拡大を目指し、超低高度にて長期間にわたり観測運用可能とする衛星技術を獲得することを目的として、超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS:Super Low Altitude Test Satellite)の開発を進め、2017年12月23日にしきさい(GCOM-C)とともにH-IIAロケット37号機にて種子島宇宙センターから打ち上げられ、軌道上運用を継続し、2019年4月より超低高度運用に移行する予定である。
つばめでは、推進効率の高いイオンエンジンを用いた超低高度での軌道保持技術を実証し、空力最小化のための構造設計や搭載機器の集約設計、並びに原子状酸素に関わる観測や小型の高分解能光学センサによる地表面観測を通じて、将来の超低高度衛星の実現に必要な技術実証やデータ取得を行う計画である。
本講演では、つばめの打ち上げ以降の軌道上運用状況について紹介する。
分光計が切り開く宇宙からの温室効果ガス観測:10年を超えたGOSAT "いぶき" による観測の軌跡とこれから
人工衛星しきさいで観測する地球の色彩
SGLIは、近紫外(380nm)から熱赤外(11μm)までを19チャンネル・250m分解能のセンサにより1000km以上の走査幅で連続広域観測する中分解能センサです。SGLIはCCDを使用した電子走査方式の光学センサ(VNR)と冷却型の赤外検知器を用いて機械走査する光学センサ(IRS)から構成されます。
人間が感じることのできない赤外線を含めた地球の持つ様々な色を継続的に繰り返し観測することにより、宇宙から四季の変化や環境の変化といった様々な物理量の変化を、地球の裏側を含めた全地球の規模で観測することができます。
本講演では、SGLIが観測する地球の様々な色彩と観測を実現する光学センサ方式・技術について解説を行います。
すばる望遠鏡で探る加速膨張宇宙の謎
我々のグループは、すばる望遠鏡用に大型のカメラHyper Suprime-Cam (HSC)を開発し、ダークマターの分布を調査することで、この問題の真相に迫りたいと考えています。
TMT主鏡について
本講演では、TMTプロジェクトの概要を紹介し、この計画に繋がるまでの望遠鏡の歴史についても簡単に触れる。次に日本の貢献の大きな柱の一つである主鏡について詳しく取り上げる。TMTの主鏡は492枚の六角形の分割鏡の組み合わせで構成される。観測中は各分割鏡の姿勢を制御し、位相を合わせることで全体として一つの大きな鏡として機能させる。この分割鏡の材料である硝材、分割鏡の外形形状・表面形状の決め方、研磨方法、支持機構、位相合わせについて解説する。また建設予定地であるハワイのマウナケア山で現在活躍しているすばる望遠鏡や、大気ゆらぎをリアルタイムで補正し回折限界の解像度の画像取得をする補償光学(Adaptive Optics; AO)についても紹介する。
光学赤外線30m望遠鏡TMTの観測装置と科学目標
本講演では、望遠鏡完成時に使われる第1期観測装置である近赤外線撮像分光装置(Infrared Imaging Spectrograph, IRIS)と可視光の広視野分光器(Wide-Field Optical Spectrograph, WFOS)の現状と今後の予定、日本の役割分担、主な科学目標について詳説する。また、これらの観測装置に続く第2期以降の観測装置の検討状況や科学目標、すばる望遠鏡をはじめとする8m級の望遠鏡や宇宙望遠鏡との連携の重要性についても概説する。

| お支払方法 |
|
●クレジットカード ●当日支払 |

|
セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/25までは受講料の50%、3/26以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

岡田 達明
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所 准教授
1991年東京大学理学部地球物理学科卒業、1996年同大学院理学系研究科修了(地球惑星物理学専攻)。博士(理学)。専門は惑星科学、惑星探査科学。これまでに従事した主な惑星探査ミッションは、小惑星探査「はやぶさ」、月周回探査「かぐや」、小惑星探査「はやぶさ2」。「はやぶさ2」では中間赤外カメラTIRの主担当のほか、観測系共通エレキDEの主担当、さらに欧州協力の小型着陸機MASCOTの日本側リエゾンとして成功に導く。帰還サンプルを分析する地球外物質研究グループも兼任。
山村 一誠
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所 准教授
1995年3月 東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修了・博士(理学)
1995年4月 日本学術振興会特別研究員
1998年4月 オランダ・アムステルダム大学研究員
1999年11月 文部科学省宇宙科学研究所助手
2006年4月 JAXA宇宙科学研究所助教授(2007年より准教授)
現在 「あかりデータ処理・解析チーム」チーム長として、赤外線天文衛星「あかり」を用いた研究推進を行うほか、次世代赤外線天文衛星SPICAの検討に参加している。個人の専門としては、恒星進化末期に起きる質量放出現象を、赤外線や電波観測により研究している。
村上 豪
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所 助教
2006年東京大学理学部卒、2011年同大学理学系研究科博士課程修了。宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所にて日本学術振興会特別研究員(PD)、宇宙航空プロジェクト研究員を経て2017年より現職。専門は人工衛星や探査機による惑星大気・プラズマの撮像観測に関する研究。月周回衛星「かぐや」や国際宇宙ステーション、惑星分光観測衛星「ひさき」、水星磁気圏探査機「みお」および水星表面探査機への搭載装置の開発に従事してきた。現在は国際水星探査計画ベピコロンボの科学代表者を務める。
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門 SLATSプロジェクトチーム
1998年 東京工業大学工学部機械宇宙学科卒業
2006年 東京工業大学大学院理工学研究科機械宇宙システム専攻博士後期課程修了(博士(工学))
同年 宇宙航空研究開発機構入社。
2006~2008年 JAXA研究開発本部にて宇宙航空プロジェクト研究員として宇宙ロボティクスの研究に従事。
2008年より、JAXA第一宇宙技術部門にて、超低高度衛星技術試験機(SLATS)プロジェクトに携わり、衛星システム(姿勢制御系)およびミッションセンサ(光学センサ)を担当。
所属学会:日本航空宇宙学会
須藤 洋志
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門 GOSAT-2プロジェクトチーム 主任研究開発員
2002年 東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了 博士(工学). 同年、国立環境研究所 NIESポスドクフェローとして温室効果ガス観測手法の開発および観測に従事. 2006年より 宇宙航空研究開発機構にてGOSAT,GOSAT-2の開発・運用・データ解析に従事.
所属学会:American Geophysical Union
田中 一広
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
GCOMプロジェクトチーム サブマネージャ
昭和61年3月 早稲田大学理工学部 電子通信学科 卒業
昭和61年4月 宇宙開発事業団 入社
平成18年よりGCOMプロジェクトにおいて光学センサの開発・運用に従事
宮崎 聡
自然科学研究機構 国立天文台
先端技術センター 准教授 理学博士
1988年 東京大学理学部物理学科卒業
1993年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻 修了
1994 - 1996年 日本学術会議振興会海外特別研究員(ハワイ大学天文学研究所)
1996 - 国立天文台助手
2007年から現職
研究テーマは,観測的宇宙論 観測装置開発
大屋 真
自然科学研究機構 国立天文台
TMT推進室 特任准教授
京都大学大学院理学系研究科で赤外線天体観測装置の開発と銀河系外天体の研究を行い1999年に博士(理学)を取得。大気ゆらぎに隠された微細な空間構造を明らかにしたいと思い、通信総合研究所(現・情報通信研究機構)においてCOE特別研究員として大気ゆらき測定と大気ゆらぎの影響を除去した画像取得の研究を始めた。その後、すばる望遠鏡に移りサポートアストロノマー、シニアサイエンティストとして補償光学装置の開発・運用に従事しその解像力を活かした天体観測を実現してきた。現在は国立天文台特任准教授・TMT推進室光学部門サブマネージャーとして、TMTの主鏡製作を担当。専門は補償光学を中心とした天体観測装置および観測天文学。
早野 裕
自然科学研究機構国立天文台
先端技術センター 准教授
1995年に博士(理学)を取得。2001年まで情報通信研究機構で地上衛星間レーザー光通信のための補償光学システムの基礎開発に従事した。その後国立天文台に移り、すばる望遠鏡のレーザーガイド星補償光学系を開発してきた。2015年8月からTMTの近赤外線撮像分光装置IRISの開発に参加し、日本が担当する撮像系開発チームを取りまとめている。