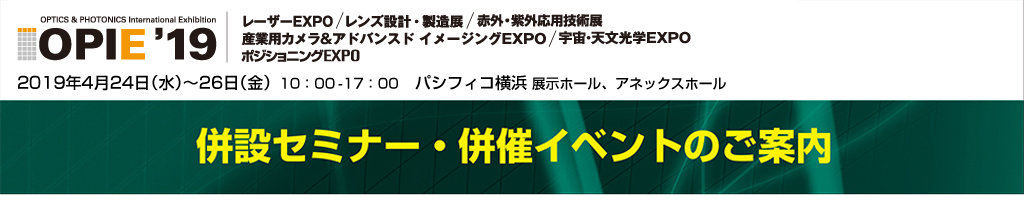・Beyond 5Gに向けた光通信技術
Beyond 5Gへ向けた光通信技術の役割
Beyond 5Gを時代には100Gbps以上の無線ピーク速度を想定する必要があり、急増するモバイルトラヒックを効率的かつ経済的に収容すべく、光ネットワーク全体としての性能向上が望まれる。本稿ではBeyond 5G時代に向けた光アクセス及びコアネットワークの役割等を紹介する。
Beyond 5Gを見据えた光アクセスシステム技術
本講演では、5Gからその先を見据えたモバイルネットワークを支える光アクセスシステム技術を紹介する。現状のFTTHでは、経済的な光アクセスシステムを構築するため局内装置や光ファイバを共用するPONが使われている。PONをモバイルネットワークへ適用することで経済的なネットワーク構築が可能となり、その適用技術を国際標準化動向と共に紹介する。また、モバイルサービスだけでなく、多数のIoTサービスの出現が予測される。そこで、モバイルサービス、IoTサービスを効率よく提供する光アクセスシステム技術についても紹介する。
RoF(Radio-over-Fiber)伝送方式を応用した5G / Beyond 5Gモバイルフロントホール
課題解決のアプローチの一つとして、基地局の機能分割点を変更するFunctional Split方式が提案されている。一方、コアネットワークでの進展が著しいSDN/NFV技術のRANへの適用が並行して検討されている。これら二つのアプローチは、多様なサービスに対して各々に最適な性能を有する仮想RANを同一ハードウェア上で提供する、RANスライシング技術に集約されると見込まれており、最近の研究開発成果を紹介する。
一方、5G成熟期~Beyond 5Gに向けてはより根本的な大容量化対策が必要となり、MFHへのRoF伝送方式の適用が検討されている。中間周波数に変換した複数のRoFチャネルを周波数多重して伝送するIntermediate Frequency-over-Fiber (IFoF) を長距離光伝送部に適用し、高い周波数利用効率を実現する。さらにIFoF信号から個別のRoFチャネルを抽出して短距離光伝送でアンテナに供給することで、アンテナサイト装置の小型化・低消費電力化が期待できる。このようなハイブリッドMFHの最近の成果を紹介する。
最後にBeyond 5Gに向けた展望として、RANスライシング技術とRoFベースMFHとの融合の可能性を示す。
100G-PONシステムに向けたデジタルコヒーレント伝送技術
一方、インターネットトラフィックの継続的な増加に伴って、PONシステムは1Gb/sから10Gb/sへの移行が進んでおり、また、日本では第5世代移動通信システム(5G)が2019年にプレサービスされることが決定し、それを支える光アクセス網の高速化は増々進んでいくとみられる。
本セミナーでは、2030年頃の運用が期待されているBeyond 5Gに向けた100Gb/s級PONシステムについて解説する。伝送速度を向上させるため、従来の強度変調方式では無く、デジタルコヒーレント伝送技術を用いた多値位相変調方式が候補の一つとして挙げられる。デジタルコヒーレント伝送技術は国際通信や国内基幹網といった大容量通信が必要なシステムで採用されている技術であり、偏波分離、位相推定等の技術について解説する。さらに、光アクセス網に適用するためには、経済的にも魅力のあるシステムを構築する必要があり、光送受信機の省電力・小型化技術について解説する。
多値変調技術とBeyond 5Gへの展開
コヒーレント光通信システム用ディジタル信号処理技術
本講演では、近年めざましい発展を遂げているコヒーレント光通信システムと、それに用いられる心臓部エンジンともいえるディジタルコヒーレント信号処理について、概要から最新技術動向までについて述べる。一波長100Gbpsから600Gbpsまで、さらにその波長数倍の伝送容量を実用化している技術と、また伝送距離と容量のトレードオフを最適化できる技術について述べる。さらに今後の展望として、大規模データセンタ間接続についての適用について、低電力化・高密度実装、異メーカ間相互接続性、新しいエコシステムに向けた動向についても概観を述べる。
機械学習を適用した光ネットワーク技術
これらの課題を解決するため、光ネットワークへの機械学習技術の適用が注目されている。
本セミナーでは、まず、上述したBeyond 5G時代の光ネットワークの課題について述べる。次に、光ネットワークの要素技術を(1)モニタリング、(2)分析・推定、(3)推奨・制御の三つに分類し、機能の解説を行う。最後に、(1)モニタリング、(2)分析・推定に対する機械学習技術の適用例について、講演者らの取り組みも含めながら、その研究開発動向を紹介する。
マルチコア光ファイバ
そこで、新たな大容量化を実現する多重軸として期待されているのが「空間」です。近年、空間多重を用いた光伝送技術は世界中で積極的な研究開発が進められており、これまでに既存光ファイバの100倍以上の情報容量を実現する成果も報告されています。光ファイバにおける空間多重とは、1本の光ファイバ内における光の通り道を増やすことに相当し、国内でも多くの研究者が様々な種類の空間多重用光ファイバの研究を推進しています。本講演では、空間多重用光ファイバの種類や特長について、最近の研究例を交えながらご紹介します。
SDM用空間結合光デバイス技術
それらの接続技術においても様々な取組みにより研究開発が進められているが、そのなかの取組の一つとしてレンズを用いた空間光学結合技術について説明させていただく。レンズを用いることで空間を伝搬する光を操作し、結合させる技術は古くから光通信デバイスに利用されてきた方式であるが、現在でも数多くの光デバイスに利用されている必要不可欠な光学技術である。MCFやFMFに空間光学系を利用する利点は、伝搬される複数の信号光に対して空間を伝搬する光に機能素子を通過させることで、1つの機能素子で複数の伝搬光に対して一括で光を操作することが可能となり、光ファイバによる伝送容量の増加に対応するだけではなく、機能デバイスの省スペース化や省力化に貢献することが期待できる。
SDM伝送用高効率EDFA
ており、光通信システムの伝送容量は増大の一途を辿っている。要の技術は波長分割
多重(WDM: wavelength-division multiplexing)技術、及び優れた信号処理技術と併せたコヒーレント検波技術である。しかし、シングルモードファイバの伝送容量は上限である約100Tb/sに接近しつつあり、商用利用可能なシステムという観点からは残り1桁以内に迫っている。そこで、来るBeyond 5G時代の膨大なトラフィックに対応する十分なシステム容量を確保すべく、マルチコアファイバ(MCF: multicore fibers)の利用を含めた空間分割多重(SDM: space-division multiplexing)技術の開拓が進められている。特に、マルチコアエルビウム添加ファイバ増幅器(MC-EDFA: multicore erbium doped fiber amplifier)は、超大容量MCF内を伝播する信号光の損失を補償するのみならず、増幅器の顕著な省電力化も可能とする。この点は、供給電力に制限がある場合や、装置が高密度集積される場合において重要なものとなる。
本講演では、SDM伝送向けの高効率MC-EDFAを紹介する。特に、効率的な光増幅の鍵となるEDFAの励起技術、すなわち、コア励起、クラッド励起及びハイブリッド励起技術に関して、その進展を述べる。

| お支払方法 |
|
●クレジットカード ●当日支払 |

|
セミナー申込手順
※有料セミナー キャンセル規程:
お客様のご都合による受講解約の場合、3/25までは受講料の50%、3/26以降につきましては受講料の全額を解約金として申し受けます。
※学生料金:
個人もしくは学校からのお支払いで、30歳未満の方が対象となります。

鈴木 正敏
株式会社KDDI総合研究所
森田 逸郎
株式会社KDDI総合研究所
中村 浩崇
日本電信電話株式会社NTTアクセスサービスシステム研究所 主任研究員
1999年3月東京大学工学部物理工学科卒。1999年4月NTT入社後、NTTアクセスサービスシステム研究所にて光アクセスシステムに関する研究開発に従事。特に、FTTHサービスで用いられているGE-PONシステムの高速化を目指して、10G級PON、40G級PON、さらにはWDM-PONの要素技術に取り組んできた。2009年より、国際標準化団体ITU-Tの活動に参加し、次世代PON技術の標準化に取り組んでいる。現在は、PONの5Gモバイルへの適用を目指した研究開発を推進している。電子情報通信学会正員。
西村 公佐
株式会社KDDI総合研究所
光アクセスネットワークグループ グループリーダー
1988年東京工業大学修士課程修了。同年国際電信電話(株)(現KDDI(株))に入社。可視発光半導体材料・素子、光信号処理技術、電子ディスプレイ応用技術等の研究開発を経て、現在はモバイルシステム用有線アクセスネットワークの研究開発に従事。2008年東京工業大学博士課程修了。電子情報通信学会シニア会員、応用物理学会およびSID会員。
斧原 聖史
三菱電機株式会社
情報技術総合研究所 主席研究員
2005年 大阪大学大学院工学研究科電子情報エネルギー工学専攻 博士後期課程修了
2005年 三菱電機株式会社 入社
以来、光通信ネットワーク(国際海底ケーブルシステム、メトロシステム、アクセスシステム)に関する研究開発に従事
現在、同社情報技術総合研究所 光技術部所属
電子情報通信学会、IEEE各会員、博士(工学)
中沢 正隆
東北大学
電気通信研究機構 特任教授
昭和55年 東京工業大学・大学院総合理工学研究科博士課程了
同年 日本電信電話公社 電気通信研究所入社
平成11年 NTT R&Dフェロー
平成13年 東北大学電気通信研究所教授
平成22年 同所長
平成23年 国立大学附置研究所・センター長会議会長、電気通信研究機構長
平成31年現在 東北大学電気通信研究機構特任教授、Distinguished Professor
IEEE、OSA、電子情報通信学会、応用物理学会の各フェロー、OSAの Board of Directors、IEEE Photonics Society, Board of Governorsを歴任。今までに490件の論文、350件の国際会議報告、および100件以上の特許を取得。また、小型EDFAを実現し様々な光通信技術に応用した業績により、IEEE Daniel E. Noble Award, Quantum Electronics Award, OSA R. W. Wood Prize, Charles H. Townes Award、紫綬褒章、日本学士院賞などを受賞。
富澤 将人
日本電信電話株式会社
NTT未来ねっと研究所 フォトニックトランスポートネットワーク研究部 部長
1992年 早稲田大学理工学研究科 修士課程修了
同年 日本電信電話株式会社入社
以来、超高速光通信システムの研究開発、実用化、国際標準化に従事し、また海外キャリアとのコラボーレーションを遂行。2008年来、国内メーカ複数社との共同研究開発(100GCoE)を牽引。
2000年 博士(工学)
2003年 米国マサチューセッツ工科大学客員研究員
2007年 光産業技術振興協会 櫻井健二郎記念賞
2010年、2014年 電子情報通信学会 業績賞
2011年、2015年 通信文化協会 前島賞
2012年 全国発明表彰 特許庁長官賞
2013年 情報通信技術委員会 総務大臣表彰
2016年 文部科学大臣 科学技術表彰 など
電子情報通信学会フェロー、米国OSAフェロー
小田 祥一朗
株式会社富士通研究所
2006年 大阪大学大学院博士後期課程了(工学博士)
2005年~2007年 日本学術振興会特別研究員
2007年 株式会社富士通研究所 入社
2011年 富士通株式会社 (兼務)
(株)富士通研究所入社以来、デジタルコヒーレント伝送システム、光パフォーマンスモニタおよび、光パフォーマンスモニタを用いた光ネットワーク制御技術の研究開発に従事。
中島 和秀
日本電信電話株式会社
主幹研究員
1994年、日本大学大学院 博士前期過程修了
同年、日本電信電話株式会社入社。
以来、各種光ファイバの設計・評価技術に関する研究開発、並びに国際標準化活動に従事。
2005年、博士(工学)
2013年、電子情報通信学会 業績賞、
2016年、前島密賞、
2017年、文部科学大臣賞
現在、日本電信電話株式会社、アクセスサービスシステム研究所、主幹研究員(上席特別研究員)・グループリーダー、並びにITU-T、Q5/SG15ラポータ。
小林 哲也
株式会社オプトクエスト
技術開発部 技術設計課 課長
1990年住友セメント(株)(現;住友大阪セメント(株)入社。
同年より(株)応用光電研究室に出向し、主に光ファイバを用いた光学製品試作製造業務を経て、光学装置及び光ファイバーデバイスの設計業務に従事。2001年より(株)オプトクエストへ入社し、光学機器及び光デバイスの開発・設計業務に従事し、2012年よりSDM関連光デバイスの研究開発に従事。
Emmanuel Le Taillandier de Gabory
日本電気株式会社
システムプラットフォーム研究所 研究部長
1999年 フランス・グランゼコール(仏最高学府)エコール・シュペリュール・ドプティック大学修士号を取得
同年にパリ第11大学修士課程修了。
2000年 富士通カンタムデバイス株式会社入社。
基幹系光ファイバ通信用光源及びトランシーバー・モジュールの開発に従事。
2007年 日本電気株式会社入社。
以来、大容量光伝送システムの研究開発に従事。
現在、同社システムプラットフォーム研究所、研究部長