
産業技術総合研究所(産総研)電子光技術研究部門主催(光産業技術振興協会(光協会)共催)の第3回電子光技術シンポジウムが2月25日(火)、東京は秋葉原UDXギャラリーで開催されました。
今回のテーマは「電子と光の融合を目指して」、サブタイトルは「ネットワークからインターコネクションへ」でした。
情報通信トラフィックは爆発的に増えています。これに伴って引き起こされる情報通信機器の電力エネルギー消費の増加が、いま大きな問題となっています。この問題を解決して情報通信社会の持続的発展を実現するには、新しい電子技術と光技術が融合して省エネルギー・低環境負荷の大容量情報通信技術の開発が必要です。
今回のシンポジウムでは産総研が関わる、フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発(PECST)、超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発(光エレクトロニクス実装)、光ネットワーク超低エネルギー化技術拠点(VICTORIES)の三つの光情報通信(光情報伝送)関連のナショナルプロジェクトを中心とした最新の研究開発成果が紹介されました。
また、広域網から機器内配線に渡る情報通信技術分野で最先端のシステム、デバイスの研究開発を展開している研究者の方々による特別講演と招待講演も行なわれ、その最新状況が披露されました。
シンポジウムで発表された優れた研究開発成果は、内外から高い評価を得ています。しかしながら、大事なのはその後の事業化です。プロジェクトに参画している民間企業が、その成果をどのようにビジネスに活かして行くのか、各社の経営陣に課せられた責任には重いものがあります。
_____________________________________________
当日の講演テーマと講演者の方々は、以下の通りです(☆印は特別講演と招待講演)。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★開会挨拶:産総研 情報通信・エレクトロニクス研究分野 研究統括 金山敏彦氏
光協会 専務理事 小谷泰久氏
★大容量光通信に向けた産総研の取り組み:
産総研 電子光技術研究部門長 原市聡氏
☆特別講演:光電子融合基盤技術の展開-FIRSTプロジェクトの成果を中心にして:
東京大学 生産技術研究所 教授 荒川泰彦氏
☆招待講演:光エレクトロニクス実装プロジェクトの狙いと開発状況:
光電子融合基盤技術研究所 サブプロジェクトリーダー 蔵田和彦氏
★CMOS技術によるシリコンフォトニクス集積:
産総研 電子光技術研究部門 堀川剛氏
☆招待講演:広帯域・高密度オンボードインターコネクトのためのGI型ポリマー光導波路:
慶應義塾大学 理工学部 准教授 石榑崇明氏
★3次元光回路:
産総研 電子光技術研究部門 森雅彦氏
★光電子ハイブリット回路基板技術開発-有機・ポリマーフォトニクス:
産総研 電子光技術研究部門 佐々木史雄氏
☆招待講演:
全世界のIDC内の総バンド幅を一台で実現するTSUBAME3.0へ向けたExtreme Big Data技術:
東京工業大学 学術国際情報センター 教授 松岡聡氏
☆招待講演:超低エネルギー光ネットワークに向けた産総研拠点の取り組み:
産総研 ネットワークフォトニクス研究センター長 並木周氏
★基幹・機器内光ネットワークの大容量化に向けた高密度周波数多重化技術:
産総研 電子光技術研究部門 山本宗継氏
★閉会挨拶:産総研 電子光技術研究部門長 原市聡氏
編集顧問:川尻多加志








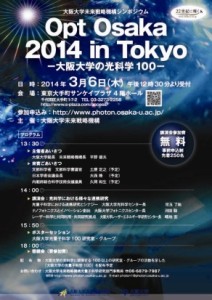




とタカハタ電子(右)のブース.jpg)


