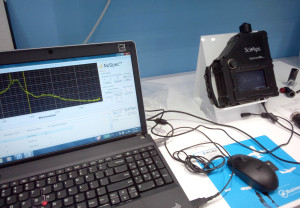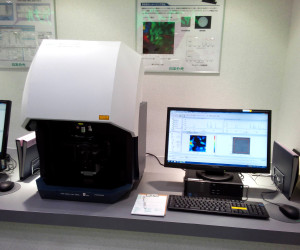光を物質に入射すると、反射、屈折、吸収などの他に、散乱という現象が起こります。散乱光のほとんどは入射光と同じ波長のレイリー散乱光ですが、ごく僅か入射光とは違う波長の光が含まれています。ラマン散乱光です。
ラマン分光装置は、このラマン散乱光の性質を調べることで物質の分子構造や結晶構造などを非接触、非破壊で調べる事ができます。無機化合物、有機物、固体、液体、気体、粉末など、私たちの回りの殆どのものを測定できて、特別な前処理も要りません。
東京ビッグサイトで先月開催された「インターフェックスジャパン」でも、このラマン分光装置がいくつか出展されていました。
サーモフィッシャーサイエンティフィックの携帯型ラマン分光分析装置「TruScan RM」は、重量が1kg以下と軽量で、どこにでも持ち運び可能、特異性と再現性の高い結果を数秒で判定します。焦点距離とスポットサイズが固定されていて、露光時間・積算回数も自動調整してくれるので、測定者によっておこる誤差もないとのことです。同社は、判定を類似性評価ではなくスペクトルのみで行なうので、完全一致判定ができるとアピールしています。容器の外からでも測定は可能です。
この他、同社では卓上タイプのDXRxiイメージング顕微ラマン、DXRレーザーラマン、DXR Smartラマンなどを取り扱っています。
スペクトリスのMalvern製「Morphologi G3-ID/G3SE-ID」は、粒子径と粒子形状の物性情報を測定する従来品にラマン分光システムを統合した複合機で、化学情報の測定もできるようになりました。アプリケーションは、医薬品やセラミックス、電池の粉砕条件の検討や効率的な結晶多形のスクリーニング、異物解析など、多岐に渡るとのことです。
リガクの携帯型ラマン分光計「Progeny」は、1064nm励起によって蛍光の重畳を防止。小型・軽量のハンディタイプで、バッテリ駆動による機動性も兼ね備え、現場に持参して迅速に化合物の同定ができます。ガラス容器や透明バッグの外からも測定が可能となっています。
ラマン分光装置は、より現場で使いやすい装置へと進化を続けているようです。
編集顧問:川尻多加志