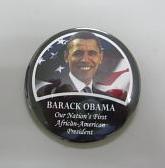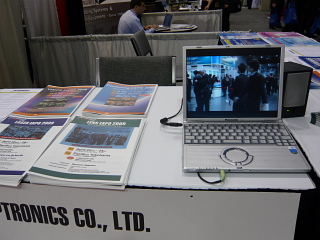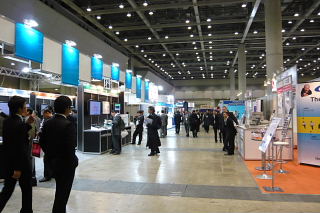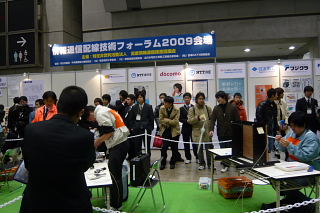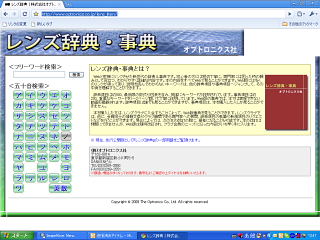今月から月に1回ペースくらいで、弊社の顧問税理士の久野幸一税理士のご許可を得て「久野会計メールマガジン&ニュース」から面白かった記事を転載させていただくことになりました。
評価が高く最近英語学習のテキストなどにも使われているオバマ大統領の演説についてのお話です。

首題のタイトルで、1月27日の朝日新聞にコラムニストの天野祐吉氏がコラムを書いています。
オバマ新大統領の就任演説を起草したのが27歳のコピーライターだッたとか言う話もありましたが、印象に残る名演説であったと思います。
天野氏は、人々を動かすのは「書かれた言葉」でなく、「語られた言葉」なのだとしており、「文字」ではなく、「声」なのだと書いている。
コラムの中で、「イエスの説得術」という本を紹介している。その説得の秘訣は、①圧縮せよ、②シンプルであれ、③くりかえせ、④誠実さを示せ、の4点にあるといってる。
演説の原稿を作るに当たって、①から③までは訓練すすれば誰でもある程度のレベルまでは到達が可能と思われますが、④の誠実さはその人の全てですから、なかなか難しいところがあります。
麻生首相は、その地位に着くまでは、自分の言葉でしゃべっていましたが、首相になってからは失言が相次ぎ、官僚の原稿を読むようになって、またその発言に注目が集まるにつれ、その人格というか誠実さの程度が透けて見えるにしたがって、情けない状態になってしまいました。
天野氏はコラムの最後に、オバマさんの就任演説を、ブッシュさんが、日本の首相が読んだらどうなるだろうか? 言葉には、とりわけ語られる言葉(生身の声)には、その人の日頃の行き方(生き方?)が、隠しようもなく映りこんでいるからこわいと結んでいる。
※(生き方?)は管理人が勝手に加えました。最後に久野税理士の似顔絵マンガは良く出来ていると思いますが、ご本人があまり気乗りでなかったので、久野税理士の名誉のため筆者と一緒に旅行した時のスナップを下に掲載しておきます。